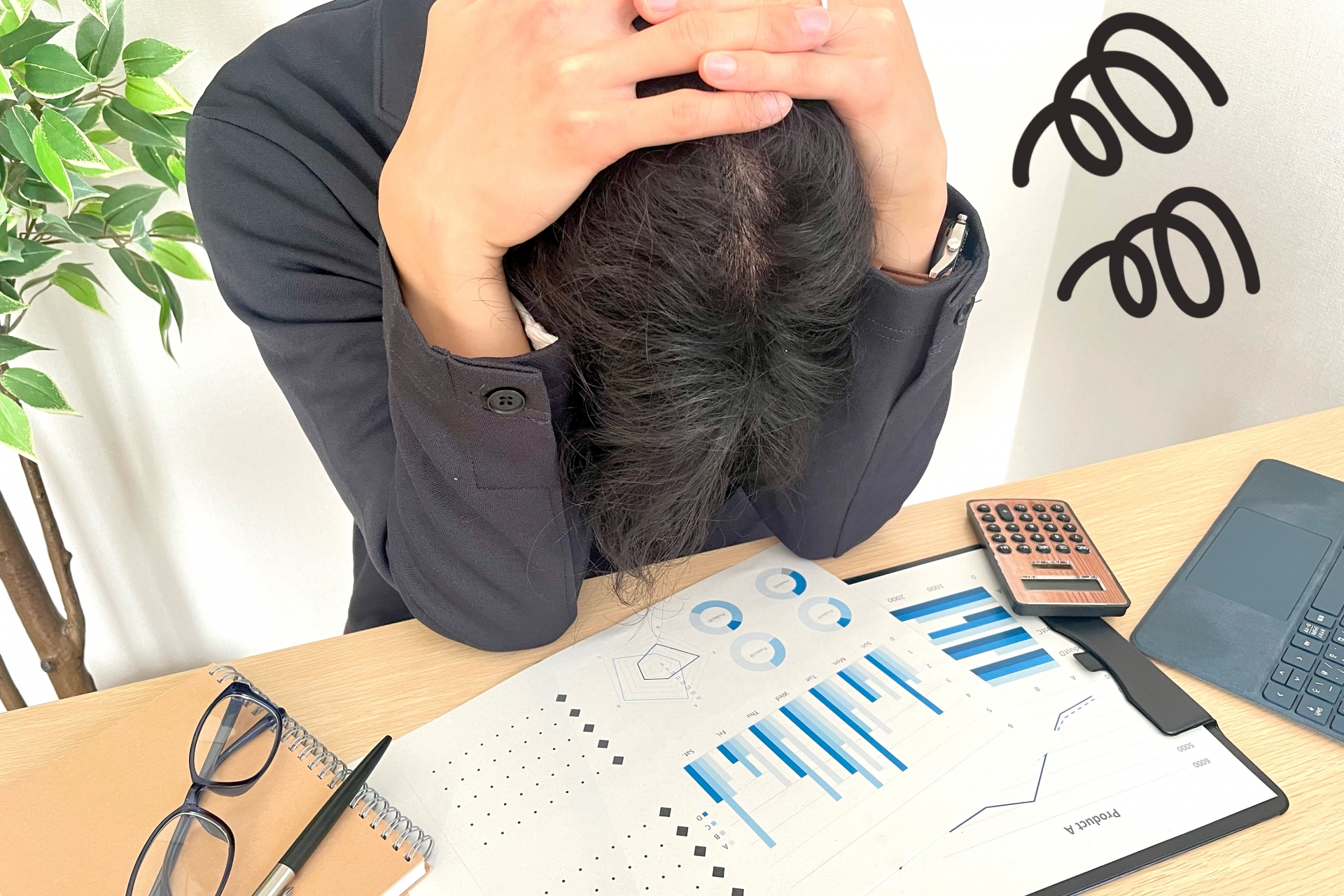同じ社内、普段からトンデモな人だと、接するときに予め気持ちの準備ができています。困るのは、人当たりが良さそうな人が、仕事で関わると鬼キャラだったりすること。高齢者ほど多い印象です。
会社の中には、いろんな人が居ます。育ちも、受けてきた教育も、社会人になってからの経験も違います。会社の勤務に対する“熱度”も違います。
職場の人間関係は大きな負担になりやすく、理想とのズレに悩むこともあります。人間関係のストレスをどう対処するかは、多くの職場で共通する課題です。この記事では、職場の人間関係の原因と改善策を紹介します。
記事を読めば、抱えているモヤモヤの正体が整理でき、自分に合った対処法を見つけるヒントが得られます。職場の人間関係の改善には、問題の本質の理解が重要です。人間関係の悩みは一人で抱え込まず、問題の本質を知ることから始めましょう。
職場の人間関係が悪化する原因

職場の人間関係が悪化する主な原因には、以下の要素が挙げられます。
- コミュニケーション不足
- 価値観の違い
- 役割や責任の不明確さ
- 嫌がらせ
- パワハラ
コミュニケーション不足
職場での人間関係トラブルの主な原因は、コミュニケーション不足です。情報共有が不十分だと認識のズレが生じ、チームワークに支障をきたします。コミュニケーション不足を招く主な要因には、以下が挙げられます。
- 日常会話の不足
- リモートワークによる交流機会の減少
- 部署間の連携の希薄さ
- 公式な対話の場の欠如
若手社員は、フォローが不十分な環境では不安や疑問を相談しにくく、心理的に孤立しやすい状況です。評価基準が不明確だと努力の方向を見失い、意欲も下がりがちです。メールやチャットでは感情が伝わりにくく、誤解を招く場合もあります。対面では表情や声から真意を読み取れ、信頼関係も築きやすくなります。
飲み会や社内イベントの減少で、関係構築の場が失われつつある点も見逃せません。
価値観の違い

職場の人間関係が悪化する要因の一つに、価値観の違いがあります。単なる意見の食い違いではなく、仕事や人生に対する根本的な考え方の差です。仕事と私生活のバランスや成功の定義、仕事の進め方などに違いが表れます。
残業もいとわず働く上司と、定時退社を望む部下の間では、仕事への姿勢にズレが生じやすく、互いに不満を抱きがちです。世代間でも、ベテランは従来のやり方や忠誠心を重んじ、若手は変化や柔軟性を求める傾向です。違いを理解せず価値観を押し付けると、不満が積み重なり関係が悪化します。
役割や責任の不明確さ
役割や責任が曖昧な職場は、人間関係の悪化を招く原因です。若手社員にとってはストレスが大きく、就職先選びを後悔する要因にもなります。職務内容が定まっていなかったり、役割分担が曖昧で押し付け合いが起こったりするケースがあります。
成果の評価基準が不透明だったり、最終決定権の所在が不明確だったりする点も注意が必要です。20代前半の社会人にとっては、役割や指示が不明確な職場環境は混乱を招きやすいものです。プロジェクトの優先順位や引継ぎ、権限と責任のバランスが曖昧だと、業務に混乱が生じやすくなります。
役割の不明確さは多くの場合、個人ではなく組織の問題です。
» 仕事を辞めたいと感じる理由と対処法を紹介
嫌がらせ

職場での嫌がらせは、人間関係悪化の深刻な原因となります。精神的ダメージを受けると、仕事への意欲も低下しかねません。職場でよく見られる嫌がらせの例として、以下のようなものがあります。
- 無視や仲間外れ
- 噂や陰口
- 不必要な批判や嘲笑
- 業務妨害や情報の遮断
- SNSやメッセージでの嫌がらせ
被害が長引くと精神的な影響が大きくなるため、見過ごさない姿勢が重要です。就職先に不安を抱える20代前半の若手にとっては、自信を失う要因にもなります。職場全体の雰囲気も悪化し、チームのパフォーマンスにまで影響します。
職場での嫌がらせは、早期の発見と対処が重要です。被害を受けていると感じたら、一人で抱え込まず、信頼できる上司や人事部門に相談しましょう。日時や内容を記録しておくと、対応がしやすくなります。
パワハラ
パワハラは職場で深刻な問題であり、多くの若手社員が被害を受けています。職場での地位や人間関係の優位性を利用し、精神的・身体的な苦痛を与える行為が該当します。2020年6月のパワハラ防止法により、企業には防止措置が義務付けられました。パワハラの典型例は以下の6つです。
- 身体的攻撃
- 精神的攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
パワハラには、暴力や暴言、無視、不可能な業務の強要、能力を否定する発言、過度なプライベート干渉などが含まれます。20代前半の社員は社会経験が浅く、パワハラを「指導」と誤解しやすいため、被害に気づきにくい傾向です。パワハラは上司に限らず、先輩や同僚から受ける場合もあります。
パワハラを受けたと感じたら、日時や内容、証人の有無の記録が大切です。信頼できる上司や人事部門、または労働局など社外の窓口に相談してください。
職場の人間関係のストレスがもたらす影響

人間関係によるストレスが及ぼす影響には、以下のような点が挙げられます。
- 精神的影響
- 肉体的影響
- 仕事のパフォーマンスへの影響
精神的影響
人間関係のストレスは心の健康に影響し、20代前半では精神的負担から就職先選びを後悔するケースもあります。不安や恐怖心は、職場での大きなストレス要因です。心の不調として、以下の状態に陥る場合があります。
- うつ症状
- 孤立感や孤独感
- 過度な自己批判
- 睡眠障害
- 悲観的思考
精神的な負担が積み重なると、社会不安障害などを発症しやすくなるため注意が必要です。イライラや怒りを周囲にぶつけてしまい、家族や友人との関係にも悪影響が及ぶ恐れがあります。精神的な負担が限界に達すると、燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥り、離職を考えるようになります。
肉体的影響

職場の人間関係のストレスは、心と体の両方に関わる問題です。若手社員の体調不良は、職場環境に起因しているケースもあります。ストレスによって現れやすい身体的な不調は、慢性的な頭痛や偏頭痛、睡眠障害などです。胃腸の不調や免疫力の低下、血圧や心拍数の上昇なども見られます。
肩こりや腰痛などの筋肉の緊張も生じやすくなります。長期的なストレスによる、自律神経のバランスの乱れが原因です。不調を放置すると慢性化し、休職や離職に至るリスクがあります。体の不調を感じたときは、職場のストレスが関係していないか、一度立ち止まって考えましょう。
» 仕事が合わないと感じる理由と対処法!
仕事のパフォーマンスへの影響
職場の人間関係によるストレスは、仕事のパフォーマンスに大きく影響します。人間関係の悪化によって集中力が乱れ、作業に時間がかかるようになるからです。仕事のパフォーマンスへの影響には、創造性の低下やチームワークの乱れ、ミスや事故の増加、欠勤や遅刻の頻発などが挙げられます。
モチベーションの低下は業務の質を下げ、顧客対応や問題解決力にも影響します。企業全体の評価に悪影響を及ぼすため、注意が必要です。ストレスを抱えた状態では冷静な判断が難しくなり、意思決定の質やスピードも落ちます。キャリアの成長機会の喪失にもつながります。
個人のパフォーマンス低下は、職場全体の生産性や雰囲気の悪化につながる要因です。
職場の人間関係を改善する方法

職場の人間関係を改善するために取り組みたいポイントには、以下の方法が挙げられます。
- コミュニケーションの改善
- 価値観の共有
- 組織文化の見直し
コミュニケーションの改善
職場の人間関係を改善するには、コミュニケーションの質の向上が有効です。挨拶や雑談を大切にすると信頼関係の土台が生まれます。新しい職場では、挨拶が関係構築の第一歩になります。改善には定期的な1on1やIメッセージ、傾聴の姿勢、明確な表現、適切なツールの活用が効果的です。
相手の話に耳を傾け「もう少し詳しく教えていただけますか?」などの質問を使えば対話も深まります。表情や姿勢などの非言語の要素にも配慮しましょう。意見の違いがあっても冷静に事実をもとに話し合う姿勢が、良好な関係づくりにつながります。
価値観の共有

職場の人間関係を改善するには、メンバー間での価値観の共有が重要です。価値観がずれていると、同じ目標に向かっているつもりでも努力の方向が食い違う場合があります。価値観を共有するためには、以下の取り組みが有効です。
- ミッションやビジョンを確認する
- 成功の定義や評価基準を明確にする
- 共通目標への意識を育てる
- チームビルディングを実施する
ただし、共有は価値観の押し付けではなく、多様性の尊重が前提です。部署間の交流を活発にすると、組織全体の一体感も高まります。リーダーが率先して価値観を示すと効果的です。
組織文化の見直し
職場の人間関係を改善するには、組織文化の見直しが欠かせません。全員が共有できる価値観と行動規範を定めることが重要です。期待のズレが減り、対人ストレスの軽減につながります。ただし、価値観はトップダウンで押し付けるのではなく、メンバー全員で築く姿勢が求められます。
職場の人間関係を改善するには、心理的安全性の確保や多様性の尊重、オープンな対話、部署を越えたコミュニケーションが効果的です。意見を言いやすい雰囲気づくりや、失敗を学びと捉える姿勢も大切です。組織文化の状態は、社内アンケートや小規模な対話を通じて定期的に確認しましょう。課題の早期発見に役立ちます。
リーダーの言動は組織文化に大きく影響し、模範的な行動を示せば周囲にも良い影響が広がります。成果だけでなく、協力やサポートも評価する制度も有効です。社内イベントや非公式な交流の場も、人間関係の構築に効果があります。
職場の人間関係改善のために個人でできること

職場の人間関係をより良くするために、以下のような個人の取り組みが役立ちます。
- 自己認識の向上
- ストレス管理
- 建設的なフィードバックの受け方
自己認識の向上
自己認識の向上は、職場の人間関係を改善する第一歩です。自分の強みや弱みを客観的に把握すると、他者との関わり方にも良い変化が生まれます。感情の傾向を把握したり、コミュニケーションスタイルを理解したり、定期的に振り返ったりすると効果的です。
「感情日記」は、自分の反応パターンを知るための助けになります。性格診断ツールも、自分を客観的に知る手段として役立ちますが、結果にとらわれすぎないことが大切です。価値観や理想の働き方を明確にすれば、行動に一貫性が出て、対人関係も安定します。
自分の役割や期待を理解したうえで、境界線を意識して適切に主張し、不要なストレスを防ぎましょう。
ストレス管理

メンタルヘルスの維持には、職場の人間関係によるストレスの適切な管理が欠かせません。ストレスをため込むと心身に不調をきたし、仕事のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。対策としては、運動や趣味、マインドフルネス、十分な睡眠、バランスの取れた食事、感情の記録などが効果的です。
20代前半の人は、仕事と私生活の線引きを意識し、自分の限界を認める姿勢が大切です。「NO」と言う勇気や、完璧を目指しすぎない姿勢も心の余裕につながります。ストレスの原因を把握し、対処法を考える習慣も有効です。信頼できる人に相談したり、必要に応じて専門家のサポートを受けたりすることも大切です。
小さな成功を認めると自己肯定感が高まり、ストレスへの耐性も強まります。
建設的なフィードバックの受け方
建設的なフィードバックは、職場の人間関係の改善と自分の成長に役立ちます。フィードバックは批判ではなく、成長の機会として前向きに受け止めます。受ける際は感情的にならず、相手の話を最後まで聞きましょう。前向きにフィードバックを生かすには、以下の行動が有効です。
- 話を最後まで聞く
- 質問して不明点を確認する
- メモを取る感謝を伝える
- 改善点を見つけて実行する
自分の価値観や状況に応じて取捨選択し、実行可能なものから取り組みましょう。定期的な自己評価で、改善の進み具合を確認すると効果的です。
職場の人間関係が改善しない場合の対処法
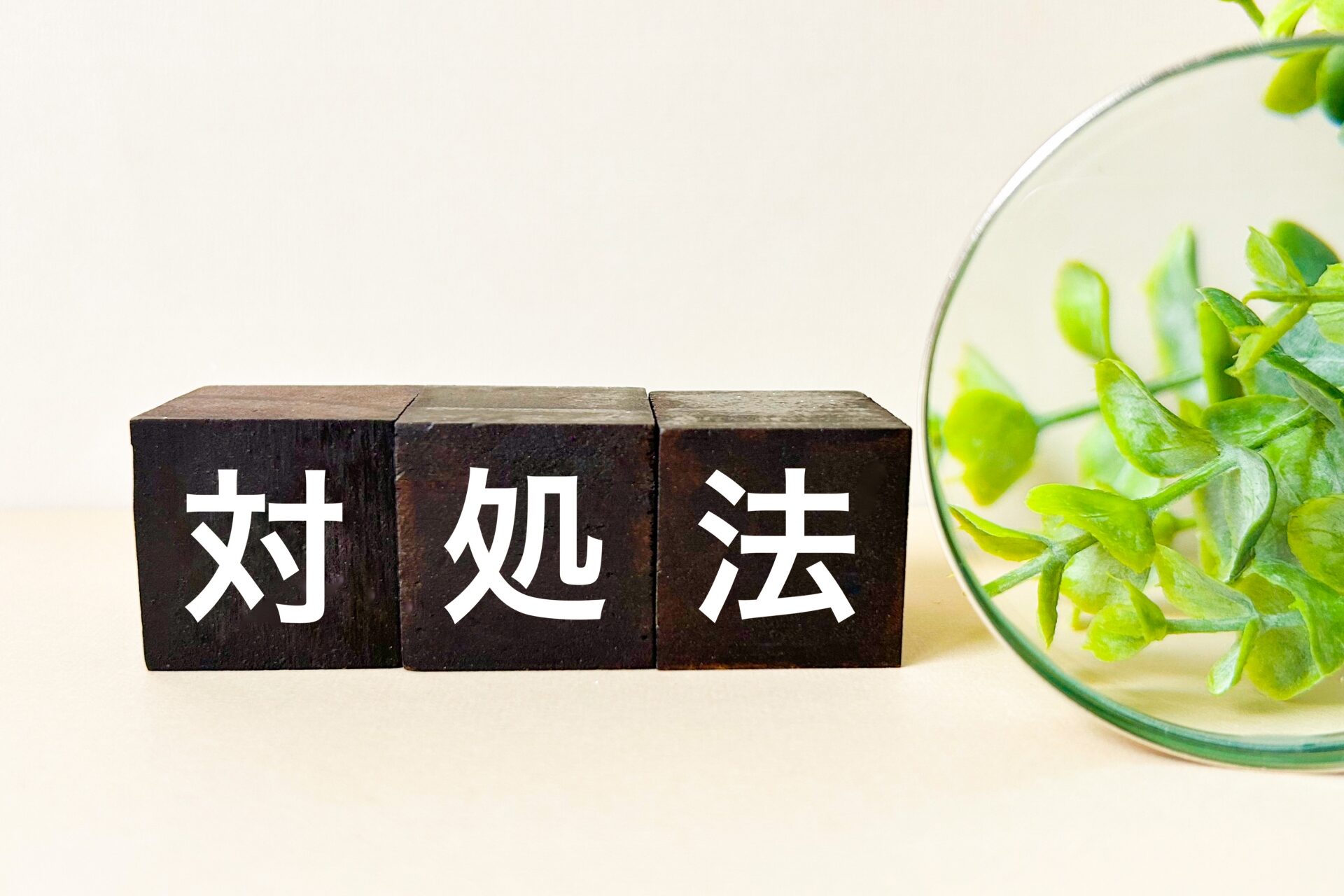
職場の人間関係が改善しない場合には、以下の対応策を検討する必要があります。
- 異動を依頼する
- 外部の専門家に相談する
- 転職する
異動を依頼する
職場の人間関係によるストレスが改善しない場合は、社内異動の検討も一つの方法です。異動により新たな環境で再出発できる可能性があります。異動を申し出る際は感情的な表現を避け、客観的な理由を整理して伝えます。異動が難しい場合に備えて、役割変更などの代替案も用意しましょう。
上司や人事に伝える際は、タイミングと配慮を意識し、具体的な提案を添えることが大切です。異動申請には社内規定があるため、手続きの流れや必要書類を事前に確認しましょう。信頼できる先輩や同僚に相談すれば、実践的なアドバイスを得られる場合もあります。
外部の専門家に相談する

職場の人間関係の悩みを一人で抱えるのは、大きな精神的負担です。外部の専門家に相談すれば、客観的な視点からのアドバイスが得られ、解決策を見つけやすくなります。職場の人間関係に関する相談先は、以下のとおりです。
- キャリアカウンセラー
- 産業カウンセラー
- 労働基準監督署
- 若者サポートステーション
- メンタルヘルスの専門家
EAP(従業員支援プログラム)を導入している企業では、専門家に無料で相談できる場合があります。深刻なハラスメントなど法的な問題がある場合は、弁護士への相談も検討してください。初回相談が無料の法律事務所もあります。専門家に相談するメリットは、第三者の視点で冷静に状況を見直せる点です。
感情に流されやすい場面でも、専門的なアドバイスが問題解決の助けになります。
転職する
転職は、職場の人間関係の問題が改善しない場合の最終手段です。あらゆる対処を試みても状況が変わらないときは、新しい環境に身を置くと心の負担を軽減できる場合があります。20代前半は専門性がまだ確立していない場合が多く、新しい分野にも挑戦しやすい時期です。
転職によって、自分に合った職場や働き方が見つけやすくなります。まずは現職の課題を整理し、自分のスキルや経験が転職市場でどのように評価されるかを把握することが重要です。転職市場の動向をリサーチし、求人情報を有効に活用しましょう。
志望先の企業風土や働き方についても事前に理解を深めておくことが、後悔のない転職につながります。ただし、環境を変えても、対人関係に課題があれば同じ問題が再発する恐れがあります。自己理解を深め、人間関係のスキルを磨きましょう。
» 【頑張っても報われない】評価されず疲れたときの選択肢を紹介
まとめ

職場の人間関係に悩んだ経験は、今後のキャリアに必ず生かせます。目の前の困難を失敗ではなく、自分を成長させる過程と捉えましょう。目先の問題に振り回されず、長期的な視点で自分にとって何が必要かを見極めてください。
人間関係の課題にどう向き合い、どう乗り越えるかの学びは、今後どの職場でも通用する力になります。必要であれば、信頼できる上司や外部の相談窓口に頼ることも大切です。自分を守る選択肢を持つことで、心にゆとりが生まれます。
新型コロナウイルス騒動の時期は「無理しなくていいんだよ」という風潮でしたが、今は、「自分のことは自分で考えよう」です。社会人である以上、マッチョ&タフな気持ちが少しでも無いと生きづらくなっています。相談できる人を確保しておく、もしくは対話型AIに個人情報がばれない範囲で相談してみるとかも良いです。