毎日会社に行くのが憂鬱で、日曜の夜から気分が沈んでしまう方は多くいます。就職したばかりの20代前半で「こんなはずじゃなかった」と感じるケースは決して珍しくありません。理想と現実のギャップに苦しむと、転職の道を考えてしまうのも当然です。
この記事では、仕事を辞めたいと感じる理由や対処法、実際に退職を決めた場合のステップまで詳しく解説します。記事を読めば、感情的にならず、自分の将来を見据えた冷静な決断が可能です。仕事を辞めるかどうかの判断は、現状の改善の可能性と転職後のキャリアプランを比較検討することが重要です。
焦って辞めるのではなく、自分自身と向き合い、最適な選択をしましょう。
仕事を辞めたいと感じる理由

仕事を辞めたいと感じる主な理由は以下のとおりです。
- 給与や待遇への不満がある
- 職場の人間関係のトラブルを抱えている
- 仕事内容が向いていない
- 労働条件が悪い
- 評価が不当だと感じる
- 社風や企業文化が合わない
- ライフスタイルが変化した
給与や待遇への不満がある
給与や待遇への不満は、多くの若手社員が感じる不満の一つです。同世代の友人と比較して自分の給与が低いと感じたり、労働時間の割に報酬が見合っていないと感じたりする場合があります。昇給やボーナスの基準が不明確であったり、福利厚生が充実していなかったりするのも不満の大きな原因です。
20代前半で生活するのに十分な収入が得られないと感じる場合、経済的な不安が大きなストレスの要因になります。給与や待遇への不満は、時間とともに蓄積され「もっと待遇の良い会社に転職したい」という気持ちが強くなります。
職場の人間関係のトラブルを抱えている

職場での人間関係は、仕事のモチベーションに大きく影響するため注意が必要です。上司からの過度なプレッシャーや理不尽な叱責、同僚との競争や軋轢などの問題が生じると、仕事へのやる気が削がれます。新入社員の場合、職場環境への適応が難しく、孤立感を抱く場合もあります。
20代前半は社会人としての経験が浅いため、職場でのコミュニケーションの取り方に戸惑いがちです。上司や先輩からの厳しい指導を受けると自信を失い「この会社では自分は成長できない」と感じてしまうケースもあります。
仕事内容が向いていない
仕事内容が自分に向いていないと感じる主な原因は以下のとおりです。
- 適性や能力とのミスマッチがある
- 達成感や充実感を得られない
- 必要なスキルと自分の強みが一致しない
- 同じ失敗を繰り返してしまう
- 求められる性格特性が自分と合わない
内向的な性格の方が常に対面営業を求められる職場では、毎日のコミュニケーションに大きなストレスを感じます。創造性を発揮したい方が単調な事務作業を続けると、仕事への情熱を失いやすいのも特徴一つです。自分の価値観や信念と業務内容が衝突すると、仕事の成果も出しにくくなり、自己効力感が低下してしまいます。
労働条件が悪い

長時間労働やサービス残業、休日出勤が常態化している職場では、心身の疲労が蓄積し、プライベートの時間が確保できません。有給休暇が取りにくい環境や不規則なシフト勤務なども、ワークライフバランスを崩す原因になります。
若手社員は「新人だから仕方ない」と考えて無理を続けがちですが、過酷な労働条件は法律で禁止されています。労働条件の悪さは単なる不満ではなく、自分の人生の質に関わる重要な問題です。
評価が不当だと感じる
職場での評価が不当だと感じるのは、仕事を辞める大きな理由になります。自分の頑張りや成果が正当に認められないとモチベーションが低下し、職場への不信感が高まるからです。20代前半の若手社員は、評価システムに不慣れであり、不当な評価に悩みやすい傾向があります。
同じ成果を出しても他の人より低く評価されると「この会社にいても成長できない」と感じてしまう場合があります。不当な評価に悩んでいる方は、評価基準について上司や人事部に質問してみましょう。
社風や企業文化が合わない

会社の社風や企業文化が自分に合わないと感じた場合は、仕事を辞めたいと思う理由になります。毎日長い時間を過ごす職場で、価値観や仕事の進め方に違和感があると、心身ともに疲れてしまうものです。社風が合わないと感じる主な原因は以下のとおりです。
- 会社の価値観や経営方針に共感できない
- 上下関係の厳しさに適応できない
- 残業や休日出勤の文化になじめない
- 意思決定プロセスに不満を感じる
- コミュニケーションスタイルが自分と合わない
チャレンジを推奨する社風を期待して入社したのに、実際は保守的で新しいアイデアが受け入れられないなどが一例です。プライベートを大切にしたいのに、飲み会参加が強制されるような文化に苦痛を感じる方もいます。社風の不一致は日々のストレスとなり、長期的にはモチベーションの低下や心の健康にも影響します。
ライフスタイルが変化した
ライフスタイルの変化は、仕事を辞めたいと感じる大きな理由の一つです。人生の節目や環境の変化により、現在の仕事と生活のバランスが取れなくなるリスクがあります。結婚や出産などの家族構成の変化は、働き方を見直すきっかけになります。子育てとの両立を考えると、勤務時間の長さや通勤時間が大きな負担です。
副業や趣味に力を入れたいと思っても、現在の仕事との両立が難しい場合もあります。ライフスタイルの変化に伴って仕事と生活の優先順位が変わるのは自然です。自分の価値観の変化を踏まえ、キャリアを見直しましょう。
仕事を辞めたいと感じたときの対処法

仕事を辞めたいと感じたときの対処法は以下のとおりです。
- 自分の感情をまず受け止める
- 辞めたい理由を明確にする
- 周囲の意見を聞く
- 辞めた後のリスクを評価する
自分の感情をまず受け止める
辞めたいという自分の気持ちは否定せず受け入れましょう。感情を無視したり抑え込んだりせず「今の自分はこう感じている」と認識しましょう。しかし、一時的な感情に流されて即断するのは避け、冷静になって考えるのが大切です。
感情を整理する方法は、日記をつけたり、信頼できる友人に話を聞いてもらったりするのが効果的です。休日や休暇を利用してリフレッシュし、心に余裕を持つのも欠かせません。自分を責める必要はありません。就職先選びに迷いを感じるのは、20代前半の多くの方が経験する悩みです。
感情は自然なものとして受け入れ、大切な情報源として活用しましょう。
辞めたい理由を明確にする

辞めたい理由を明確にするのは、今後のキャリア選択において重要です。感情的な判断だけで行動すると、後悔する可能性が高くなります。以下の不満や問題点を整理しましょう。
- 給与や待遇面での不満
- 職場の人間関係に関する問題
- 仕事内容と自分の適性の不一致
- 労働時間や休日の条件
- 評価制度に関する不満
書き出した不満点に優先順位をつけてください。どの問題が最も自分にとって重大か、ランク付けすると本当の退職理由が見えてきます。「解決可能な問題」と「解決不可能な問題」を区別するのが大切です。現在の職場内で改善できる問題なのか、会社を変えないと解決しない問題なのかを見極めましょう。
周囲の意見を聞く
就職先に不満を感じているとき、1人で悩み続けるよりも、周囲の意見を聞くことが問題解決の糸口になります。客観的な視点を得ると、自分では気づかなかった解決策が見つかる可能性があるからです。信頼できる家族や友人に相談してみましょう。
家族や友人は、自分の性格や価値観を理解しているため、感情面もサポートしてくれます。「この会社に向いていないのでは?」と思っていても、外部の視点からは「もう少し頑張れば道が開ける」と見える場合もあります。メンターや業界の先輩、キャリアカウンセラーなど専門的なアドバイスを求めるのも効果的です。
辞めた後のリスクを評価する

仕事を辞める前には、退職後のリスクをしっかり評価しましょう。感情的な判断ではなく、現実的なリスクを理解すると、より良い決断ができます。20代前半の場合は貯蓄が少ない場合が多いため、経済的なリスクは大きな問題になります。
転職市場の競争は予想以上に厳しいです。経験が浅い20代前半では、希望する条件の仕事に就ける保証はありません。空白期間が長くなると、スキルや経験が古くなるリスクも考えられます。辞めた後のリスクを事前に評価すると、退職のタイミングや次の行動計画をより現実的に立てられます。
» 退職におすすめのタイミングは?転職を成功させるコツを紹介
仕事を辞める前にやるべきこと

仕事を辞める前にやるべきことは以下のとおりです。
- 部署異動や配置転換を相談する
- スキルアップの勉強を始める
- リフレッシュタイムを設ける
部署異動や配置転換を相談する
部署異動を相談する際の効果的なアプローチは以下のとおりです。
- 現在の不満を建設的に伝える
- 自分の強みを活かせる部署を提案する
- 会社にとってのメリットを説明する
- 感情的にならず冷静に話す
- 具体的な希望時期を伝える
職場への不満を放置せず、社内での異動や配置転換の可能性を探りましょう。
» 退職の伝え方と適切なタイミング
スキルアップの勉強を始める

転職や職場改善を考える前に、自分自身のスキルアップを始めましょう。新しいスキルを身に付ければ、現在の職場での評価が上がったり、将来の転職に備えたりできます。現在の仕事に関連したスキルを磨くと、職場での評価向上だけでなく、自信にもつながります。
パソコンスキルやコミュニケーション能力の向上は、ほとんどの職場で有効です。空いた時間を使って業界の専門書や雑誌を読むのも効果的です。知識が増えると、会議での発言や提案の質が高まり、周囲からの見方も変わります。
リフレッシュタイムを設ける
仕事を辞めたいと思うほどのストレスや疲労を抱えているときには、リフレッシュタイムを設けるのが効果的な対処法です。心身をリセットする時間を確保すれば、冷静な判断力が戻ります。定期的な休息は仕事のパフォーマンスを上げるだけでなく、メンタルヘルスの維持にも重要な役割を果たします。
有給休暇を計画的に使うのも大切です。日本では有給消化率が低い傾向にありますが、心身の健康のためには遠慮なく使うべきです。長期休暇を取ると、仕事に対する視点が変わる場合が多くあります。自然の中で過ごす時間も効果的です。都会の喧騒から離れて、森や海、山などで過ごすとストレスホルモンが減少します。
仕事を辞めると決めた場合のステップ

仕事を辞めると決めた場合に踏むべきステップは以下のとおりです。
- 上司への退職意向の伝達
- 退職願・退職届の準備
- 業務引継ぎと挨拶
- 退職後の手続き
上司への退職意向の伝達
退職の意向を上司に伝えるのは、退職プロセスの最初の重要なステップです。会話の結果によって、退職手続きがスムーズに進むかどうかが決まります。退職を伝える際には、事前の準備が大切です。自分の気持ちを整理し、冷静な状態で臨みましょう。感情的になると建設的な会話ができません。
退職希望日は法定の2週間より余裕を持たせましょう。退職理由を伝える際は、会社や上司の批判を避けるのが重要です。会話では、これまでの経験に感謝の気持ちを示すのが大切です。「〇〇さんの下で働けて多くのことを学べました」といった言葉を添えると、良い印象を残しつつ円満な退職につながります。
退職願・退職届の準備

退職願や退職届は、退職の意思を正式に会社に伝えるための重要な書類です。適切に準備すると、スムーズな退職手続きが可能になります。退職願・退職届を準備する際に含めるべき基本情報は以下のとおりです。
- 会社の代表者宛ての正式な宛名
- 氏名と所属部署
- 作成日付
- 具体的な退職希望日
- 簡潔な退職理由
退職届の書式が指定されているか、人事部に確認しましょう。多くの企業では独自のフォーマットを用意しています。退職届に指定の書式がない場合は、インターネットで一般的なテンプレートを探して活用できます。退職理由は「一身上の都合により」など、簡潔な表現で構いません。詳細な理由は不要です。
» 退職代行とは?仕組みとメリット・デメリット、利用の流れ
業務引継ぎと挨拶
退職が決まったら、業務引継ぎと挨拶は丁寧に行う必要があります。自分の評判を守るだけでなく、会社や同僚への感謝と敬意を示す大切な機会です。業務引継ぎは計画的に進めましょう。引継ぎ書類を作成し、日常業務の手順や重要なポイントを詳細に記録してください。
後任者との直接的な引継ぎ時間を十分に確保するのがポイントです。実際の業務を一緒に行いながら説明すると、文書だけでは伝わりにくい細かなコツや注意点も共有できます。取引先や顧客との関係性についても、特記事項や過去のやり取りの経緯などを丁寧に説明しましょう。
長年築いてきた信頼関係を後任者へスムーズに引き継ぐのは、会社にとっても大きな価値があります。
退職後の手続き

退職後はさまざまな手続きが必要です。必要な手続きを適切に行わないと、健康保険や年金などの社会保障に空白期間が生じたり、不必要な費用が発生したりします。退職後に必要な主な手続きの流れは以下のとおりです。
- 健康保険の切り替え手続き
- 年金の切り替え手続き
- 雇用保険の手続き
- 住民税の支払い方法確認
- 源泉徴収票と離職票の保管
健康保険の切り替えは、退職日から14日以内に行う必要があります。役所の国民健康保険窓口で手続きを行いましょう。健康保険証やマイナンバーカード、通知カード、身分証明書を持参すると手続きがスムーズになります。年金についても、退職後は国民年金に切り替える手続きが必要です。
» 退職後に必要な5つの手続きをわかりやすく解説!
まとめ
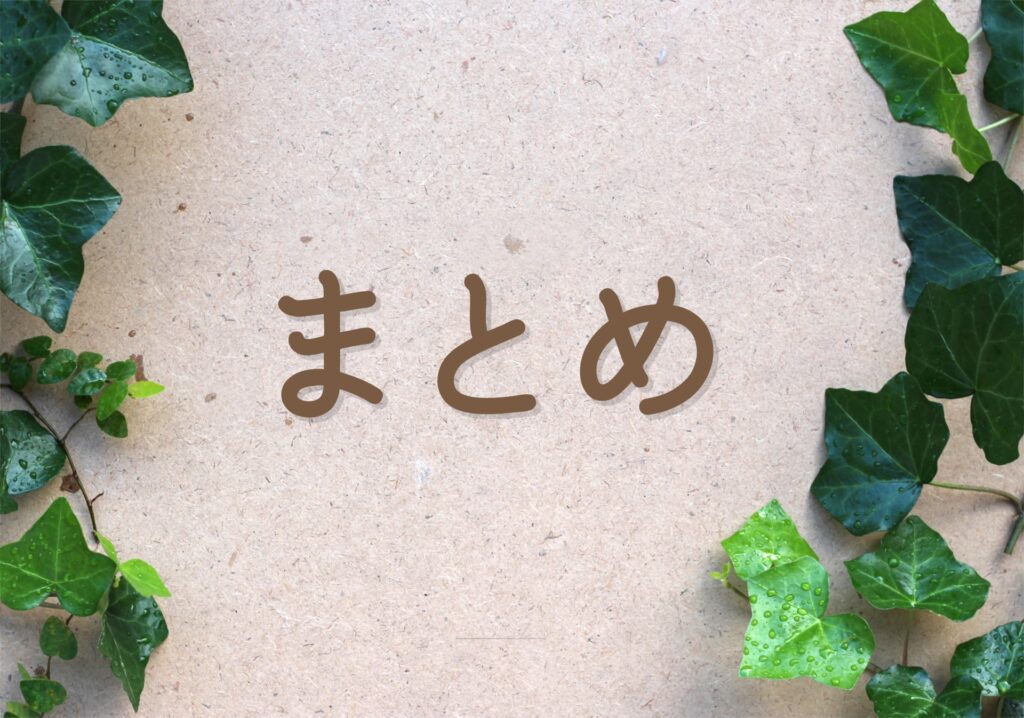
仕事を辞めたい感情は20代前半の方に限らず、誰にでも起こりうるものです。仕事を辞めたくなったら理由を冷静に分析し、感情と事実を区別して考えましょう。退職をすぐに決断する前に、社内での部署異動や業務内容の変更、リフレッシュ時間の確保といった選択肢も検討しましょう。
退職を決めた場合は、計画的に準備を進め、周囲への配慮を忘れないでください。20代前半はキャリア形成の途中であり、一度の就職選択で人生が決まりません。失敗と思える経験も、長い目で見れば貴重な学びになります。本記事で紹介した内容を実践すれば、より良いキャリア選択が可能です。








