退職金は大切な資金ですが、受け取り方や税金の扱い、運用方法に関して多くの人が不安を抱えています。この記事では、退職金のもらい方や税金、運用方法について解説します。記事を読めば、自分に最適な退職金の受け取り方や運用方法を見つけられ、将来の経済的な不安を軽減することが可能です。
退職金は一時金や年金として受け取ることも、両方を組み合わせることも可能です。
退職金のもらい方の種類

退職金の受け取り方法には、以下の3種類があります。
- 一時金として受け取る方法
- 年金として受け取る方法
- 一時金と年金を併用する方法
一時金として受け取る方法
退職金は、一時金として一括受取が可能です。一度に大きな金額を手にでき、運用や使い道を自分で決められます。一時金として受け取る場合は、長期的な資金計画が大切です。インフレリスクにも注意が必要です。自由度が高い反面、リスクを伴うため、退職後の生活設計や将来の目標に合わせて慎重に検討しましょう。
年金として受け取る方法

年金として退職金を受け取る方法は、長期的な生活設計に適した選択肢です。毎月定額を受け取る「確定年金方式」と、運用しながら受け取る「変動年金方式」があります。特徴は以下のとおりです。
- 受取期間を5年・10年・15年から選択できる
- 65歳以降の受取開始が一般的である
- 受取開始年齢を60歳以降で自由に設定できる
退職後の安定収入源として活用できますが、金利変動リスクを考慮する必要があります。長期的な視点で安定した生活を送りたい人におすすめです。
一時金と年金を併用する方法
一時金と年金を併用して退職金を受け取る方法は、柔軟性が高いのが特徴です。一部を一時金として受け取り、残りを年金として受け取れます。生活資金や負債返済用の一時金を受け取りつつ、生活設計に応じて年金調整や税金対策を考慮した組み合わせを選べます。
併用方法のメリットは、一時金と年金の良い点を活かせることです。退職後の生活状況や経済環境の変化に応じて、一時金と年金の割合を柔軟に設定できるのも特徴です。健康状態や家族構成なども考慮して、自分に最適な組み合わせを選びましょう。
退職金のもらい方別のメリット・デメリット
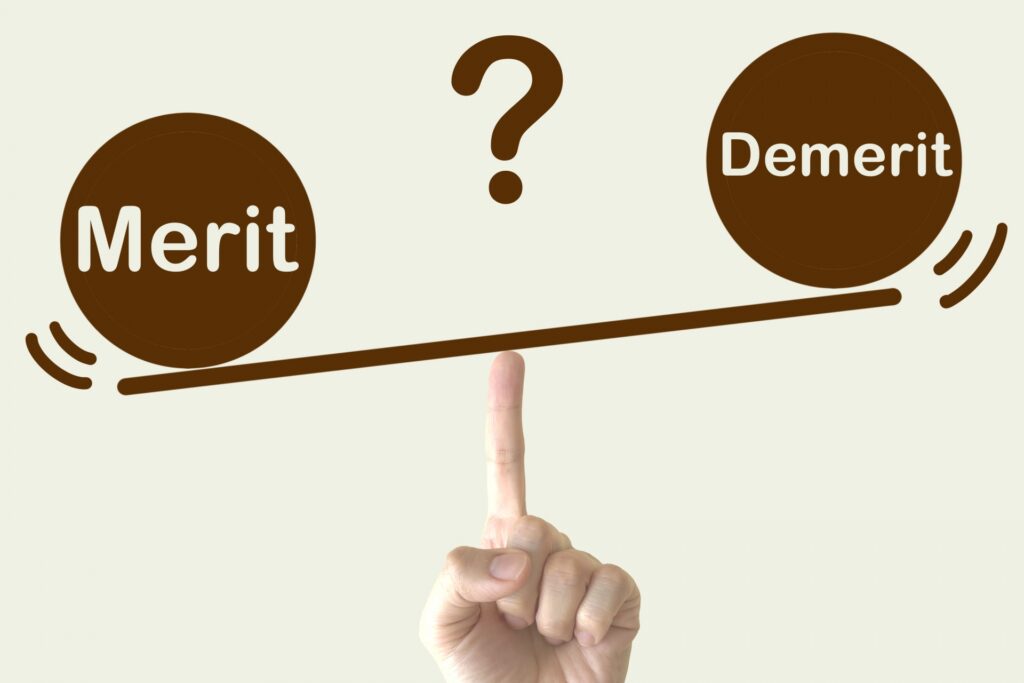
退職金の受け取り方法それぞれにメリット・デメリットがあります。以下の項目ごとに解説します。
- 一時金のメリット・デメリット
- 年金のメリット・デメリット
- 併用受け取りのメリット・デメリット
一時金のメリット・デメリット
一時金として退職金を受け取るメリットは、以下のとおりです。
- まとまった金額を一度に受け取れる
- 自由に使える資金として活用できる
- 住宅ローンの返済や事業資金に充てられる
- 投資や資産運用の原資として活用できる
- 急な出費に対応できる
デメリットは、以下のとおりです。
- 一度に多額の税金を支払う必要がある
- 使い切ってしまうリスクがある
- 運用を誤ると資産を失う可能性がある
- 長期的な収入源としては不向きである
計画性がないと、将来の生活設計が難しくなります。一時金での受け取りは、自己管理能力が必要です。
年金のメリット・デメリット

年金として退職金を受け取る方法は、インフレに強く、長生きリスクに対応できるのがメリットです。税制優遇があり、遺族が年金を受け取れる可能性もあります。運用リスクが低いのも特徴です。ただし、年金は一度決めると変更が難しい点がデメリットです。インフレ率が高い場合、実質的な価値が下がる可能性もあります。
受給開始年齢まで待つ必要があり、早期死亡の場合は損をする可能性もあります。運用利回りが低い可能性があることや、年金支給元の経営状況に依存することもデメリットです。
併用受け取りのメリット・デメリット
併用受け取りを選ぶと、生活設計に合った資金の受け取り方ができ、短期的な資金需要と長期的な生活資金の確保を両立できます。リスク分散効果を得られるのも特徴です。一時金と年金を組み合わせると、金融市場の変動リスクを軽減できます。一時金と年金の組み合わせ方によっては、税負担を抑えられる可能性があります。
ただし、管理が複雑になるのがデメリットです。最適な組み合わせを決めるには、専門的な知識が必要です。一時金部分には、運用リスクがあります。自己運用する場合、市場の変動により元本割れの可能性があるため、注意してください。一時金の割合を増やすと、年金の受給期間が短くなる可能性があります。
金融機関によっては、併用できる選択肢が限られる場合もあるため、注意が必要です。
退職金をもらうときにかかる税金と控除

退職金をもらうときにかかる税金と控除について、以下の項目ごとに解説します。
- 退職金の税金の仕組み
- 一時金で受け取る場合の控除
- 年金で受け取る場合の控除
退職金の税金の仕組み
退職金にかかる税金は「退職所得」として扱われ、一般的な所得とは別に税金が計算される仕組みです。退職金の課税方式は「分離課税」と呼ばれ、他の所得と合算せずに単独で税額が計算されます。会社が源泉徴収の形で天引きするのが一般的ですが、退職金が高額な場合は確定申告が必要です。
役員退職金は、一般従業員とは異なる計算方法が適用される場合があります。退職金規程にもとづいて支給される場合は、原則として退職所得として扱われます。規程に反する支給の場合、給与所得として扱われる可能性があるため、注意してください。
一時金で受け取る場合の控除

一時金で退職金を受け取る場合には退職所得控除額が適用されるため、税金の負担を軽減することが可能です。計算方法は勤続年数によって異なります。勤続年数が20年以下の場合は、40万円に勤続年数を掛けた金額が控除されます。
20年を超える場合は、800万円に70万円×(勤続年数-20年)を加えた金額が控除の対象です。控除後の金額の2分の1に対して課税が行われ、所得税と住民税が対象となります。所得税は分離課税方式で計算され、住民税は一律10%の税率が適用されるのが特徴です。
退職金を受け取る際には、会社から退職所得の源泉徴収票が発行されます。源泉徴収票を使って確定申告すると、税金の還付を受けられる場合もあります。
年金で受け取る場合の控除
年金で退職金を受け取る場合、公的年金等控除が適用され、税金の負担を軽減することが可能です。65歳未満の場合は最大120万円、65歳以上の場合は最大220万円の控除が適用されます。ただし、受給額が330万円を超えると控除額が減少するため注意が必要です。
年金として受け取る退職金は、雑所得として課税されます。所得税と住民税で控除額が異なるため、気をつけてください。年金収入以外の所得が多いほど、控除額が減少します。公的年金等以外の年金は雑所得として扱われ、公的年金等控除は適用されません。退職所得控除も適用されません。
退職金をもらう際の注意点

退職金を受け取る際の注意点について、以下の項目ごとに解説します。
- 自己都合退職時の退職金の扱い
- 退職金をもらえない場合の対処法
- 会社に確認すべきポイント
自己都合退職時の退職金の扱い
多くの企業では、自己都合退職時の退職金は、会社都合退職と比べて減額されます。会社の人員計画に影響を与えたり、引継ぎ準備期間が短くなったり、予期せぬ支出が発生したりすることが理由です。退職金の具体的な金額や条件は、会社の退職金規程によって決まります。
勤続年数や退職理由によって支給条件が変わる場合があります。退職を考えている人は退職金規程を確認し、人事部門に相談したうえで、必要に応じて交渉するのがおすすめです。自己都合退職でも満額支給される場合もあるので、事前に確認しましょう。
退職金をもらえない場合の対処法

退職金をもらえない場合、労働基準法や就業規則を確認し、退職金の支給条件を正確に把握しましょう。条件を満たしているのに支給されない場合は、労働組合や社内の相談窓口に相談するのがおすすめです。対処法は以下のとおりです。
- 人事部門との交渉
- 特別手当や功労金の要請
- 未払い残業代や有給休暇の買い取り
- 再雇用や業務委託契約の検討
解決しない場合、転職先での条件交渉時に退職金相当額を考慮してもらうのも一つの手段になります。退職金制度がない会社の場合は、自己資金で退職金積立を行うことをおすすめします。退職金の代替として、iDeCoやNISAなどの資産形成を行うのも良い方法です。
どうしても解決できない場合は、最後の手段として、労働審判や訴訟の検討も選択肢になります。
会社に確認すべきポイント
退職金をもらう際、会社に確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 退職金の支給額
- 支給時期と支払い方法
- 計算方法
- 一時金と年金の選択肢
- 税金の取り扱い
- 退職理由による支給額の変動
- 受け取り手続き
- 関連書類の提出期限
人事部門や上司に確認しておくと、退職金に関する不安や疑問を解消できます。会社によって退職金制度は異なるため、自社の制度をよく理解することが大切です。不明点があれば、遠慮せずに質問しましょう。
もらった退職金の賢い運用方法

退職金のおすすめの運用方法は、以下のとおりです。
- iDeCo
- NISA
- 外貨預金
iDeCo
iDeCoは個人型確定拠出年金制度で、老後の資産形成に役立ちます。税制優遇が最大の特徴です。掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税となります。受け取る際にも税制優遇があるので、長期的な資産形成に適しています。
20歳以上60歳未満の日本居住者が加入でき、毎月の掛金上限額は職業によって異なるため注意が必要です。60歳まで積立可能で、自己責任で運用商品を選択します。iDeCoは金融機関や証券会社で加入することが可能です。運用商品は投資信託や預金など、さまざまな選択肢があります。
原則として途中解約はできないため、長期的な視点で取り組みましょう。転職や退職時も継続できるので、キャリアの変化に左右されずに資産形成を続けられます。
NISA

NISAは、少額投資非課税制度の略称で、2024年から新NISAに移行しました。「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠があり、条件に応じた投資が可能です。生涯投資枠として合計1,800万円まで非課税で運用できます。新NISAでは、非課税期間が無期限となり、柔軟な運用が可能です。
NISAでは、株式や投資信託、ETFなどに投資でき、18歳以上の日本に住んでいる人なら誰でも利用できます。口座の開設は、銀行や証券会社などの金融機関で簡単にできます。運用益や配当金が非課税になる一方で、損失が出ても税金の控除は受けられません。
途中解約やお金の引き出しは自由で、売却した分の生涯投資枠は翌年以降に再利用できます。金融機関を変更する際には制限があるので注意してください。NISAは、通常の課税口座と併用して利用可能です。投資を始めたばかりの人でも始めやすく、長期的な積立投資に適しています。
外貨預金
外貨預金は為替変動によるリターンが期待できるため、資産の増加につながる可能性があります。外貨建て資産による分散投資や、日本より金利が高い国の通貨で運用できることがメリットです。ただし、為替変動によって損失が出る可能性があるため、注意が必要です。手数料や為替スプレッドにも気をつけてください。
外貨預金には定期預金と普通預金があり、複数の通貨で運用できます。オンラインバンキングで簡単に開設できるので便利です。為替予約を使えば、リスクを抑えられます。外貨預金を始める際は、為替動向や世界経済の情報をしっかり調べましょう。円安のときに始めると有利です。
定期的に運用状況を確認して、必要に応じて見直すことをおすすめします。
退職金のもらい方に関するよくある質問
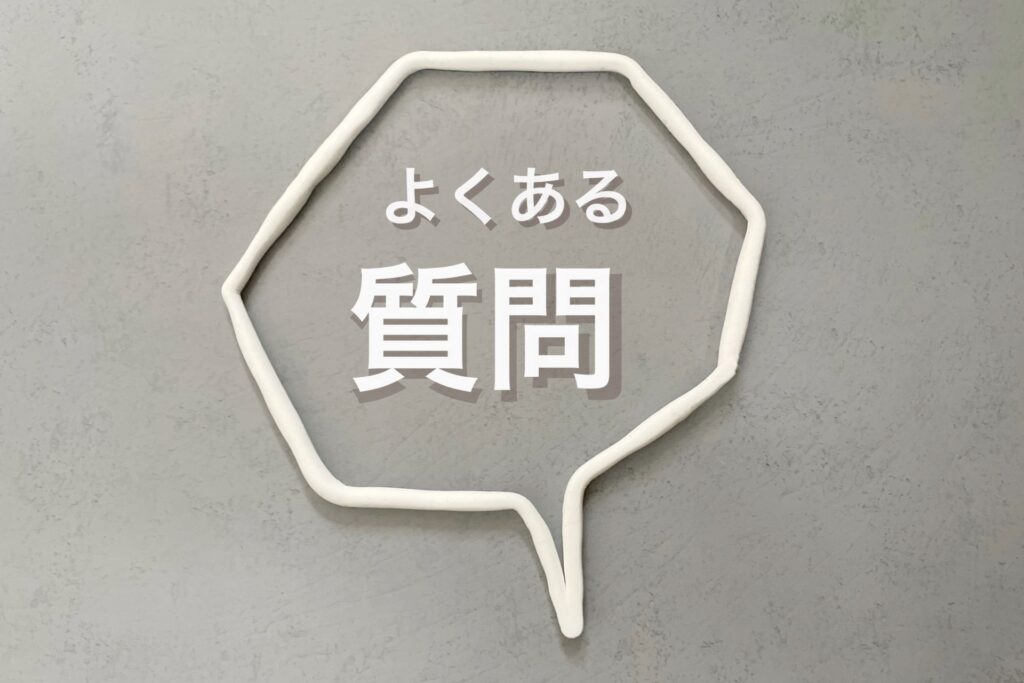
退職金のもらい方に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 退職金が支払われるタイミングは?
- 退職金の計算方法は?
- 転職時の退職金の取り扱いは?
退職金が支払われるタイミングは?
通常、退職金は退職日から1か月以内に支払われますが、会社によって異なります。以下のようなパターンがあります。
- 退職日当日
- 退職日から数週間以内
- 退職金規程に明記された日
退職金の支払い時期は、会社の退職金規程に明記されている場合が多いです。会社の資金繰りの都合で、分割払いになる可能性もあります。支払いが遅れる場合は、会社に確認しましょう。自己都合退職の場合は、退職金が支払われない場合もあるので注意が必要です。
会社都合の退職や定年退職の場合は、通常通り支払われるのが一般的です。年金として受け取る場合は、退職後に定期的に支払われます。
» 退職金はいつもらえる?勤務先別にもらえる時期を解説
退職金の計算方法は?

退職金の計算方法は「基本給×勤続年数×支給率」で算出されます。ただし、実際の計算方法は会社によって異なるので注意が必要です。退職金の金額に影響を与える要素は、以下のとおりです。
- 勤続年数
- 役職
- 退職理由
- 会社の業績
計算方法は退職金規程や就業規則に記載されているので、自社の規程を確認してください。中小企業退職金共済制度を利用している中小企業の場合、別途計算方法が適用されます。一部の企業では功績倍率を加味したり、退職時の年齢によって調整係数を適用したりする場合もあります。
退職金の上限額を設定している会社もあるため、注意が必要です。
» 退職金の相場|計算方法から税金までわかりやすく紹介!
転職時の退職金の取り扱いは?
基本的に、前職での退職金を転職先に引き継げません。ただし、中小企業退職金共済制度(中退共)に加入していた場合は、転職先でも引き継げます。確定拠出年金(企業型DC)も、転職先で継続可能です。確定給付企業年金(DB)は、一時金として受け取るか、年金として据え置くかを選択できます。
転職先の退職金制度や条件も、事前に確認しましょう。退職金の取り扱いについて不明点がある場合は、税理士や金融アドバイザーなどの専門家に相談するのがおすすめです。
まとめ

退職金のもらい方には一時金・年金・併用の3種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。税金がかかりますが、控除制度を利用できるので上手に活用しましょう。自己都合退職や退職金がもらえない場合の対処法を知っておくことも大切です。
退職金に関する詳細を会社に確認し、iDeCoやNISA、外貨預金などで活用することで、効果的に運用できます。支払い時期や計算方法、転職時の取り扱いなど、基本的な情報をしっかり把握しましょう。退職金は将来の生活設計に大きく影響するので、自分の状況に応じて最適な受け取り方を選択してください。








