退職後の手続きが複雑で戸惑う人は多くいます。この記事では、退職後に必要な手続きを網羅的に解説します。記事を読めば、健康保険や年金、失業保険、税金など、退職後に必要な手続きを理解し、スムーズに進めることが可能です。退職後の手続きは、基本的に期限が設けられています。
手続きを怠ると不利益を被る可能性があるため、計画的に進めることが重要です。退職が決まったら、必要な手続きの全体像を把握し、優先順位をつけて進めましょう。
退職後に必要な手続きの基礎知識
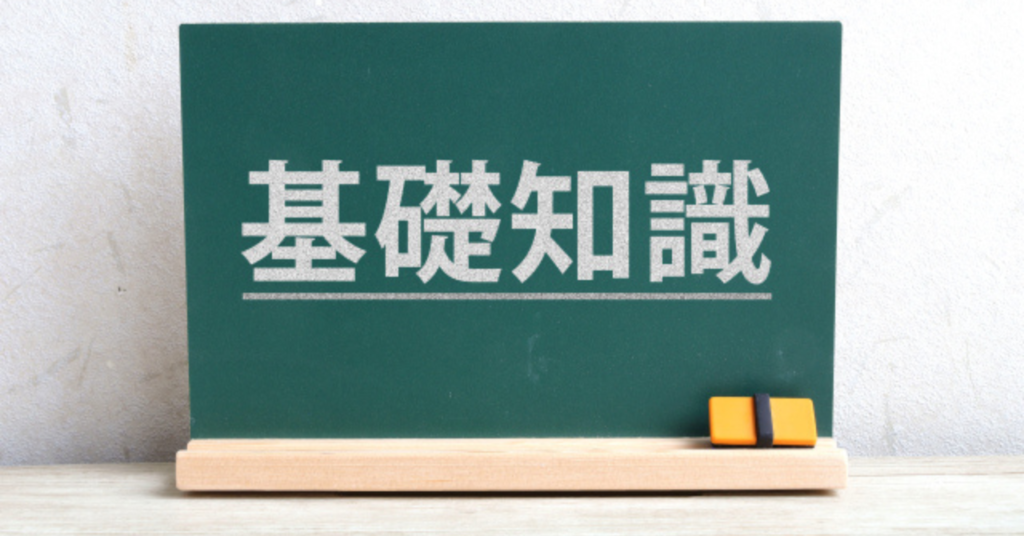
退職後に必要な手続きの基礎知識を、以下の項目に分けて解説します。
- 手続きを早めに行う重要性
- 手続きの期限とペナルティ
手続きを早めに行う重要性
早めに手続きをすると、手続きの遅れによる不利益や混乱を避けられます。健康保険や年金の空白期間を防げるため、万が一の際にも安心です。失業保険の受給開始を早められることで、経済的な不安も軽減できます。税金関連の手続きを迅速に進められる点もメリットです。
手続きを早期に完了させると、新生活の準備や就職活動に集中できます。落ち着いた環境で、必要な書類の準備や情報収集が可能です。手続きの締め切りに余裕をもって対応でき、不明点や疑問点を解消する時間的余裕も生まれます。予期せぬトラブルにも対応しやすくなるため、精神的なストレスが軽減できるでしょう。
手続きの期限とペナルティ
退職後の手続きの種類によって期限が異なるので、注意が必要です。主な手続きの種類と期限、遅延した場合のペナルティは以下のとおりです。
| 手続きの種類 | 期限 | 遅延した場合のリスク |
| 健康保険 | 退職後14日以内 | 無保険状態になる |
| 年金 | 退職後2週間以内 | 将来の年金受給額に影響が出る可能性がある |
| 失業保険 | 退職後1年以内 | 受給権が消滅する |
| 住民税 | 退職時に一括納付または分割納付の手続き | 延滞金が発生する |
| 所得税の確定申告 | 翌年2月16日~3月15日まで | 加算税が発生する可能性がある |
期限内の手続きにより、不利益を避けられます。健康保険や年金の手続きは早めに済ませましょう。
退職後の健康保険の手続き
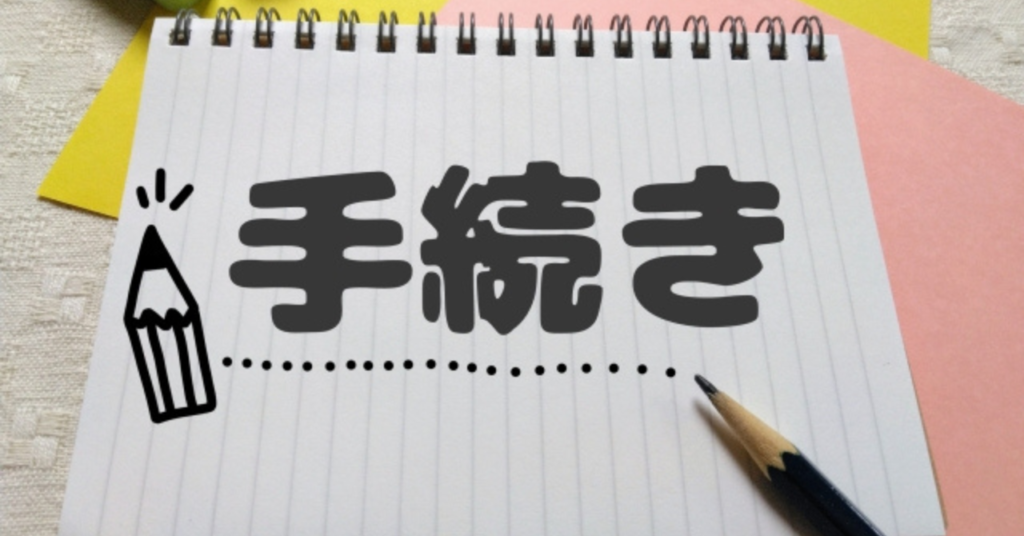
退職後の健康保険の手続きは以下のとおりです。
- 健康保険任意継続制度への切り替え手続き
- 国民健康保険への加入手続き
- 配偶者の扶養に入る場合の手続き
健康保険任意継続制度への切り替え手続き
健康保険任意継続制度は、退職後も引き続き以前の勤務先の健康保険に加入できる制度です。退職日から20日以内に手続きをする必要があります。健康保険組合または協会けんぽに申請書を提出し、必要書類を準備しましょう。保険料の支払い方法を決めます。ただし、注意点もいくつかあります。
保険料は全額自己負担となり、最長2年間しか継続できません。保険料は前年の給与をもとに計算されるため、退職前よりも高くなる可能性があります。65歳以上の人は後期高齢者医療制度に移行するので、制度を利用できません。任意継続を中止したい場合は資格喪失届を提出する必要があります。
手続きが完了すると、マイナ保険証にデータが反映されます。マイナ保険証を使わない場合は、健康保険の資格確認書が送付となります。資格確認書は、医療機関での受診時に必要となるので、大切に保管しましょう。
国民健康保険への加入手続き

国民健康保険への加入手続きは、退職後14日以内にしなければなりません。市区町村の窓口で世帯主が手続きをして、加入者全員の情報を申告します。必要な書類は以下のとおりです。
- 健康保険資格喪失証明書
- 本人確認書類
- マイナンバーカードまたは通知カード
保険料は前年の所得をもとに計算され、支払い方法は口座振替や納付書です。所得が低い場合、保険料の減額制度を利用できる可能性があります。
手続き完了後、マイナ保険証にデータが反映されるのは、約1−2週間後です。健康保険証の新規発行は終わっているので、マイナ保険証を使わない場合は、保険の資格確認書が約1-2週間後に郵送されます。
データ反映もしくは確認書の到着までに医療機関を受診する必要がある場合、マイナ保険証の場合は健康保険窓口にデータ反映を確認、資格確認証の場合は有資格証明書を健康保険窓口に発行して貰う必要があります。
転居時は、転出先の市区町村で再度加入手続きが必要になるため、注意が必要です。
配偶者の扶養に入る場合の手続き
配偶者が勤務先で加入している健康保険の、被扶養者となることも可能です。配偶者の勤務先の人事部門に連絡をして、必要な手続きを確認しましょう。退職証明書や年金手帳、マイナンバーカードを準備したら、以下の書類を記入のうえ提出してください。
- 扶養異動届
- 健康保険被扶養者異動届
- 国民年金第3号被保険者関係届
手続きが完了したら、配偶者の会社から新しい健康保険証の適用およびマイナ保険証へのデータ反映を待つと同時に、自身の健康保険証を返却します。反映まで約1-2週間かかります。
マイナ保険証を使わない場合は、自身の健康保険証を返却し、保険の資格確認書の到着を待ちます。配偶者の扶養控除等申告書の更新で、税金面での扱いが変更されます。
退職後の年金の手続き

退職後の年金の手続きは以下のとおりです。
- 国民年金への切り替え手続き
- 配偶者の扶養に入る場合の手続き
- 企業年金から個人年金へ移行する場合の手続き
国民年金への切り替え手続き
国民年金に切り替える場合は、退職後14日以内に、居住地の市区町村の国民年金窓口で手続きをしてください。必要な書類は年金手帳や退職証明書、本人確認書類です。国民年金保険料の納付方法を、口座振替やクレジットカード、納付書から選択します。
保険料は月額16,980円(2024年度時点)で、納付期限は翌月末日です。経済的に困難な場合は、保険料の免除や猶予制度の申請も可能です。前納制度を利用すると保険料が割引になります。海外に移住する予定がある場合は、忘れずに任意加入の手続きをしましょう。
たいていは国民健康保険と国民年金の手続き窓口は役所内で近い場所にあります。同じタイミングで引き続き手続きすることが一般的ですが、年金のみを年金事務所でも手続きができます。都合の良い方法を選んでください。
配偶者の扶養に入る場合の手続き

配偶者が会社員や公務員など厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)であれば、国民年金の第3号被保険者になれます。配偶者の勤務先の人事部門に連絡をして必要な手続きを確認しましょう。退職証明書や年金手帳、マイナンバーカードを準備したら、以下の書類を記入のうえ提出してください。
- 扶養異動届
- 健康保険被扶養者異動届
- 国民年金第3号被保険者関係届
手続きが完了したら、配偶者の会社から新しい健康保険証を受け取ると同時に、自身の健康保険証を返却します。配偶者の扶養控除等申告書の更新で、税金面での扱いが変更されます。
企業年金から個人年金へ移行する場合の手続き
企業年金から個人年金への移行手続きは、現在加入している企業年金の受給資格を確認しましょう。年金事務所や勤務先の人事部門に問い合わせるとわかります。企業年金の脱退一時金請求書を入手し、必要事項を記入します。住民票や印鑑証明書などの必要書類も準備しましょう。
記入した請求書と必要書類は、企業年金基金に提出します。個人年金の加入手続きをしましょう。個人年金の種類や掛け金の支払い方法を決めてください。可能であれば、企業年金から個人年金への資金移管を依頼できます。税制優遇措置の適用可否を確認し、個人年金の運用方法を選択しましょう。
将来の受給方法は、一時金または年金から選択します。手続きは複雑で時間がかかるため、早めに進めましょう。わからないことがあれば、専門家に相談してください。
退職後の失業保険の受給条件と手続きの流れ
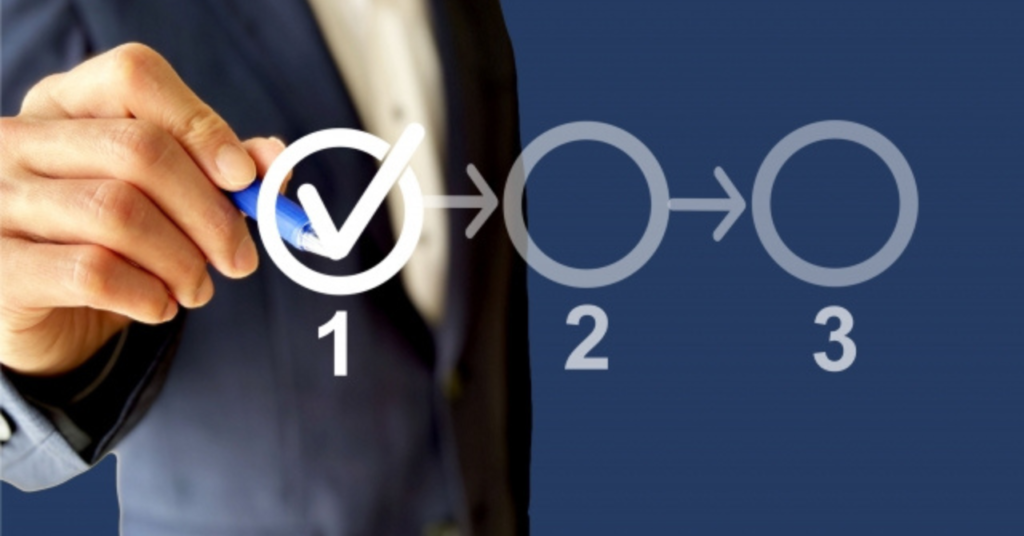
退職後の失業保険の受給条件とハローワークでの手続きの流れを解説します。
失業保険の受給条件
失業保険の受給には、いくつかの条件を満たす必要があります。雇用保険の加入期間については、原則として離職日以前の2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。ただし、倒産や解雇などによる離職の場合、離職日以前に1年間の被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を満たします。
退職理由は、自己都合退職や定年退職、契約期間満了などの労働契約の終了、倒産や解雇である必要があります。受給は、働く意思と能力があることが前提です。ハローワークでの求職申し込みや職業相談など、積極的な求職活動も条件です。原則65歳未満といった年齢制限も満たす必要があります。
妊娠や出産、育児などですぐに働けない場合は受給期間の延長が可能です。病気やけがですぐに働けない場合は、傷病手当を受給できる場合があります。定年や契約期間満了による離職の場合は特例があるため、該当する場合は確認しましょう。
ハローワークでの手続きの流れ
ハローワークに来所して求職申込書を記入しましょう。本人確認書類と離職票を提出する必要があります。求職申込書には、希望する職種や勤務条件などを記入してください。失業認定申告書の記入方法について説明を受けた後、雇用保険説明会に参加し、失業保険制度の説明を聞きましょう。
説明会で、初回の失業認定日が決定されます。決められた失業認定日にハローワークに来所し、失業認定を受けると、失業給付の支給が決定されます。2回目以降の失業認定日には、求職活動状況を報告してください。就職が決まった場合は、就職証明書を提出しましょう。
所定給付日数分の受給が終了するまで、継続して手続きが必要です。
退職後の住民税と所得税の手続きと計算方法

退職後の住民税と所得税の手続きと計算方法を、以下の項目に分けて解説します。
- 住民税の支払い方法の変更手続き
- 所得税の確定申告の手続き
- 退職金にかかる税金の計算方法
住民税の支払い方法の変更手続き
住民税の支払い方法を変更する手続きは、普通徴収への切り替えが一般的です。勤務先に退職の連絡をし、支払い方法の変更を申請してください。居住地の自治体で普通徴収への切り替え手続きをして、納付書を受け取ります。支払い方法の選択肢は以下のとおりです。
- 金融機関やコンビニでの支払い
- 口座振替
- 分割納付
住所変更がある場合は、新居の自治体にも届け出が必要になります。特別徴収から普通徴収への切り替え時期も確認しましょう。納税通知書を受け取り、内容を確認します。支払い期限を把握し、遵守してください。
所得税の確定申告の手続き

所得税の確定申告の手続きは、税務署またはe-Taxの利用で、確定申告書を入手します。確収入や所得控除、税額控除などを記入し、源泉徴収票や医療費の領収書などの必要書類を添付します。申告書の提出方法はe-Taxや郵送、税務署への持参から選択可能です。納税または還付の手続きをします。
申告書のコピーと関連書類は、将来の参考になるので大切に保管してください。確定申告の期限は通常2月16日~3月15日までです。ただし、還付申告の場合は早めに提出できます。期限後の申告は延滞税や加算税がかかる可能性があるため注意が必要です。
なお、退職時に会社側より手続き済の場合、年末調整済であれば問題ありません。今後、12月末までに就業があった場合、会社に源泉徴収票を提出すれば引き継がれます。その他、毎年のように確定申告でふるさと納税や医療費控除、10-12月頃に証明書が発行される社会保険料控除、住宅ローン控除などを受ける必要がある場合は確定申告が必要になります。
退職金にかかる税金の計算方法
退職金にかかる税金の計算方法の流れは以下のとおりです。
- 退職金から退職所得控除額を引く
- 結果の金額を2で割る
- 所得税率を適用する
- 復興特別所得税(2.1%)を加える
- 住民税(一律10%)を加える
退職金の税金計算には、勤続年数に応じた退職所得控除額が適用されます。ただし、役員退職金の場合は異なる計算方法を使用するため注意が必要です。退職金が少額の場合は非課税になる可能性もあります。退職金の支払い方法によっては、税金の計算が変わる場合があるので確認しましょう。
» 退職金の相場|計算方法から税金までわかりやすく紹介!
確定申告で精算が必要な場合もあるので注意してください。
退職後の確定申告の手続き

退職後の確定申告の手続きを、以下の項目に分けて解説します。
- 確定申告が必要なケース
- 年内に転職した場合の手続き
- 転職しなかった場合の手続き
確定申告が必要なケース
退職後の確定申告が必要となる主なケースは以下のとおりです。
- 給与所得が2,000万円を超える場合
- 給与以外の所得が20万円を超える場合
- 2か所以上から給与を受け取っている場合
- 年の途中で退職し再就職していない場合
- 退職金を受け取った場合
副業や投資で収入がある場合は、確定申告の対象となる可能性が高くなります。医療費控除を受けたい場合やふるさと納税をした場合も、申告が求められるため気をつけましょう。住宅ローン控除や寄付金控除を受けたい場合も、確定申告の必要があります。
年内に転職した場合の手続き

年内に転職した場合、前職と現職の給与所得を合算して申告する必要があるため、年末調整の書類提出期限に間に合うようであれば、現職の担当者に前職の源泉徴収票を提出しましょう。
提出期限に間に合わない場合、確定申告の手続きが必要です。前職と現職の両方から源泉徴収票を入手します。確定申告書の「給与所得の内訳」欄に両社の給与を記入し、医療費控除や住宅ローン控除などの適用があれば、忘れずに申告してください。
自身で確定申告する必要があるとき、確定申告の期限は翌年の2月16日~3月15日までです。土曜、日曜を挟む年は1-2日、前後します。早めに準備を進めてください。
退職金を受け取った場合は、退職所得の源泉徴収票も必要になります。不明な点がある場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
e-Taxを利用すれば、自宅からオンラインで申告できます。還付金がある場合は、早めの申告で早期に還付を受けられる可能性があるため検討してください。
転職しなかった場合の手続き
転職しなかった場合でも、確定申告の手続きが必要になる場合があります。年末調整だけでは税金の精算が完了しない場合は、以下の手続きが必要になります。
- 源泉徴収票の入手
- 確定申告書の作成
- 所得控除の確認と申請
- 医療費控除の計算と申請
- 寄付金控除の計算と申請
- 住宅ローン控除の申請
確定申告書はe-Taxまたは税務署へ提出してください。還付申告の場合は還付金を受け取り、納付が必要な場合は納税します。確定申告関連書類は、税務署からの問い合わせに備えるため、5年間保管してください。
まとめ

退職後の手続きは複雑で多岐にわたりますが、適切な対応が大切です。健康保険や年金の切り替えや、失業保険の受給手続き、税金関連の処理などが挙げられます。手続きには期限があるので、早めに取り掛かりましょう。注意すべきは、以下の項目です。
- 健康保険の選択
- 年金の切り替え
- 失業保険の受給手続き
- 住民税と所得税の支払い方法の選択
- 確定申告の必要性
手続きを怠ると、予期せぬ不利益を被る可能性があるので注意してください。退職後の手続きについて不安がある場合は、専門家に相談しましょう。








