退職金がいつもらえるかは、退職を決断するうえで重要な要素です。退職金に関する知識が不足していると、適切な判断ができない可能性があるため、注意が必要です。この記事では、退職金がもらえる時期や基本的な情報、税金への影響などを解説します。
記事を読めば、退職金に関する疑問が解消され、将来の資金計画を立てる際の参考にできます。退職金は、退職時または退職後数か月以内に支給されるのが一般的です。勤務先や退職理由によっても、支給時期や金額は異なります。記事を参考に、退職に向けて必要な情報を集めましょう。
退職金はいつもらえる?勤務先別に解説

以下の勤務先別に、退職金の支給時期を解説します。
- 一般企業の場合
- 公務員の場合
- 中小企業退職金共済制度の場合
一般企業の場合
一般企業の場合、退職金は退職後1〜3か月以内に支給されます。支給時期に影響を与える要素は、以下のとおりです。
- 就業規則
- 労働契約の規定
- 会社の経営状況
- 退職金規定
- 退職理由
- 退職時期
大企業では退職後すぐに支給されることが多い一方で、中小企業では資金繰りの関係で遅延する場合があります。退職金前払い制度を導入している企業では、在職期間中の受け取りが可能です。自己都合もしくは会社都合の退職によっても、異なる場合があります。
退職金の計算に時間がかかる場合や、年度末の退職では、支給が翌月以降になる可能性があります。
公務員の場合

公務員の退職金は一般企業と比べて制度が整っており、支給基準が明確です。安定した制度のため、長期的なキャリアプランを立てやすい特徴があります。定年退職する場合と勤続20年以上で退職する場合に受給が可能です。退職日の翌月末までに一時金として支給され、まとまった金額を受け取れます。
退職金の額は、退職日の給料月額と退職理由別支給率、勤続期間の区分ごとの調整率を掛け合わせて計算されます。自己都合退職では支給率が減額され、病気退職や定年退職の場合は高くなるのが特徴です。国家公務員と地方公務員では、計算方法が若干異なる点に注意が必要です。
詳細については、各自治体や所属機関の人事部門に確認してください。
中小企業退職金共済制度の場合
中小企業退職金共済制度は、中小企業で働く労働者のための国の退職金制度です。勤続年数1年以上で受給資格が発生し、掛金は事業主が全額負担します。年齢制限がなく、20代前半でも加入可能です。退職金は退職後20日以内に支給されます。
月額掛金は5,000~30,000円の範囲で選択可能で、退職金は掛金と運用利益によって決まります。掛金は非課税で、給付金に対して退職所得控除がある点は、労働者にとってのメリットです。転職しても通算できるため、キャリアアップを目指す若い世代にも適しています。
転職先選びの際は、中小企業退職金共済制度の対象かどうかを一つの基準にできます。
退職金がもらえる時期を決定する要因

退職金がもらえる時期を決定する主な要因は、以下のとおりです。
- 企業の方針
- 就業規則
- 退職理由
企業の方針
多くの企業では、以下の点について独自の方針を設けています。
- 退職金の計算方法
- 退職金の支給条件
- 退職届提出から支給までの期間
- 一括払いか分割払いかの選択肢
企業の財務状況によっては、支給時期が遅れる可能性もあります。退職を検討し始めた時点で、企業の方針を確認しておきましょう。
就業規則

就業規則では、退職金の支給条件や金額、計算方法などの重要な事項が明確に定められています。前もって確認しておくと、退職手続きの流れや必要な書類なども把握できます。就業規則の内容がわかりにくい場合には、人事部門に問い合わせましょう。退職金に関する疑問を解消すれば、将来の計画を立てやすくなります。
退職理由
退職理由は、大きく分けて会社都合と自己都合に分類されます。会社都合とは、労働者の意思とは関係なく、会社の経営状況によって引き起こされる理由です。会社の業績悪化によるリストラや、経営破綻による倒産などが挙げられます。自己都合は労働者の意思や事情によるもので、以下の理由が当てはまります。
- キャリアアップ
- 結婚・出産
- 家族の介護
- 健康上の理由
退職理由は、退職金の支給や次の就職先での評価に影響を与える可能性があるため、慎重に考えましょう。ただし、20代前半で就職先選びに失敗したと感じている場合は、早めの決断も大切です。転職により、自分に合った職場環境や仕事を見つけるチャンスを得られます。
» 退職の伝え方と適切なタイミング
退職金のもらい方による税金の違い

退職金のもらい方による税金の違いについて、以下に分けて解説します。
- 一時金でもらう場合
- 年金でもらう場合
- 併用してもらう場合
一時金でもらう場合
退職金を一時金でもらうと、まとまった金額を一度に受け取れるため、生活設計の幅が広がる点がメリットです。退職所得控除額が適用され、税金面での優遇も受けられます。使い道は自由に決定でき、生活資金や住宅ローンの返済に充てられるメリットもあります。
退職金が高額な場合は税負担が大きくなり、相続税の課税対象になる場合もある点には注意が必要です。一時的に多額の現金を管理する必要も生じます。退職後すぐに資金が必要な場合には一時金が適していますが、同時に長期的な資金計画も検討しましょう。
年金でもらう場合
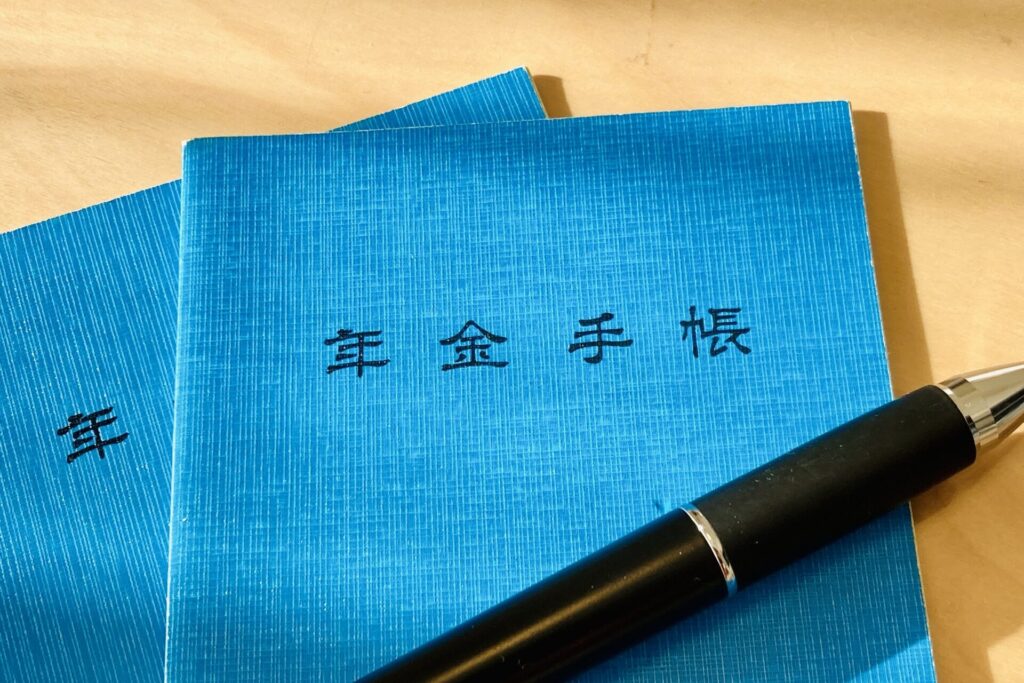
年金で退職金をもらう場合は、毎月または年1回などの頻度で定期的に受け取ります。10年や20年などの受取期間の設定が可能です。年金は雑所得の扱いになるため、一時金で受け取るよりも税負担が軽減されます。安定した収入源にでき、長期的な資金計画が立てやすい点も特徴です。
年金の運用リスクは企業側が負うため、受け取る側の負担が軽減されます。受取期間中に死亡した場合は、残りの年金を遺族が受け取れる場合もあります。インフレの影響で将来的に受け取る実質的な金額が下がるリスクには、注意が必要です。会社が倒産するリスクも考えておく必要があります。
併用してもらう場合
退職金を一時金と年金の両方で受け取る方法もあります。柔軟な資金管理と、安定した収入の両立ができる点がメリットです。一時金部分はまとまった資金を自由に運用できる一方で、年金部分は安定した収入源として使用できます。税制や経済状況の変化に応じて柔軟な調整も可能です。
一時金と年金の比率は、退職後の生活設計に応じて自由に決められます。金融機関の専門家のアドバイスを受けながら、運用方法を決めるのもおすすめです。
退職金がもらえない場合の対応策

退職金がもらえない場合には、会社の担当者に確認したり、労働基準監督署へ相談したりして対応することが大切です。
会社の担当者に確認する
会社の担当者に確認すれば、問題の原因を特定し、適切な対応策を講じられます。担当者には以下の点を確認しましょう。
- 退職金の支給予定日
- 支給条件や金額の詳細
- 退職金規定の内容
- 支給が遅れている理由と今後の見通し
状況によっては、分割払いなどの代替案を提案することも検討できます。担当者との話し合いの際は、担当者の連絡先を確認し、書面での回答を求めましょう。話し合いが難航する場合は、上司や人事部門への相談も依頼できます。粘り強く交渉を続ければ、問題解決の糸口が見つかる可能性があります。
» 退職手続きの流れをわかりやすく解説!
労働基準監督署へ相談する
労働基準監督署では、専門家に無料相談が可能です。必要に応じて労働審判や民事訴訟の手続きについて説明してもらえます。労働基準法違反の可能性がある場合には、企業への調査や指導も行われます。相談内容は秘密厳守のため、会社に知られる心配はありません。
相談時間には制限があるため、効率的に相談することが大切です。相談したい内容を整理し、関連書類も準備しておきましょう。複雑な案件の場合は、弁護士や社会保険労務士への相談も検討できます。
退職金の相場
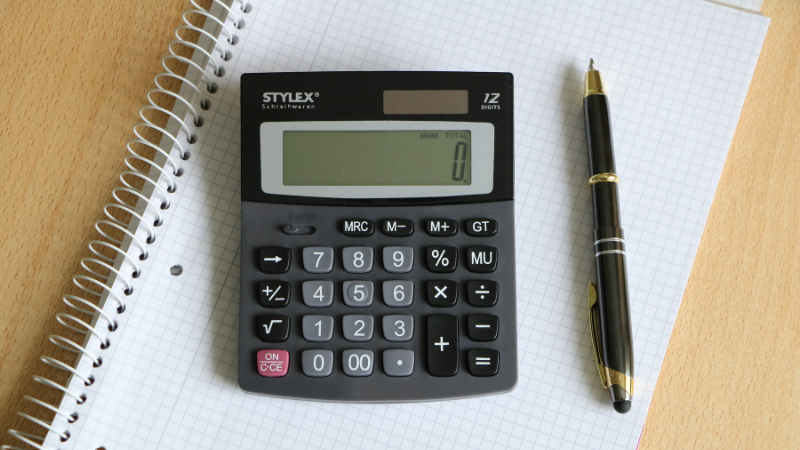
退職金の相場について、業種別、勤続年数別に解説します。
» 退職金の相場|計算方法から税金までわかりやすく紹介!
業種別の相場
業種別の退職金相場は、以下のとおりです。
| 業種 | 平均退職金 |
| IT業界 | 300〜500万円 |
| 金融業界 | 500〜1,000万円 |
| 小売業 | 100〜300万円 |
| サービス業 | 150〜350万円 |
| 製造業、建設業、医療・福祉業、不動産業 | 200〜450万円 |
退職金は、個人の勤続年数や役職、会社の業績などによっても大きく変動します。同じ業界内でも企業規模や経営方針によって差があります。自分の退職金の相場を知ることは、将来の資金計画を立てるうえで重要です。ただし、相場を知って不安になったり、他の業界と比較して落ち込んだりする必要はありません。
退職金は長年の労働の対価の一部ですが、金額だけが評価のすべてではないことも理解しましょう。
勤続年数別の相場
勤続年数が長くなるほど、退職金の額は増える傾向にあります。一般的な相場は、以下のとおりです。
| 勤続年数 | 平均退職金 |
| 勤続3年未満 | 50万円 |
| 3〜5年 | 100〜150万円 |
| 5〜10年 | 200〜300万円 |
| 10〜20年 | 400〜600万円 |
| 20〜30年 | 700〜1,000万円 |
| 30年以上 | 1,200〜1,500万円 |
退職金の額は役職や業績、企業の規模によっても差が生じます。近年は退職金制度がない企業も増加傾向にあります。就職や転職時には、退職金制度の有無を確認しましょう。
もらった退職金の資産運用の方法

もらった退職金の資産運用の方法として、定期預金と投資信託、NISAを紹介します。
定期預金
定期預金は、退職金の運用方法として安全で確実な選択肢です。元本が保証されているため、大切な退職金を失うリスクがありません。1,000万円までの預金保険制度もあります。預け入れ期間は1か月~10年程度で、一定期間預け入れると利息が得られます。
金利は普通預金より高いですが、他の投資方法よりは低めなのが特徴です。インターネットバンキングで簡単に開設できる点も、定期預金の魅力です。
投資信託やNISA
投資信託やNISAは、長期的な資産形成に役立ちます。投資信託は、複数の投資家から集めた資金をプロが運用する金融商品です。分散投資が可能なため、リスクを軽減できます。専門知識がなくても始められ、少額から投資できる商品が多いため、初心者にも適しています。NISAとは、少額投資非課税制度のことです。
NISAを利用すると、年間360万円、合計1,800万円までを非課税で投資できます。投資信託やNISAを利用する場合は、自分のリスク許容度に合わせて商品を選ぶことが大切です。定期的に投資状況を確認しつつ、長期的な視点で運用する必要もあります。投資には常にリスクが伴います。
退職金からの中から生活資金や緊急時の予備資金を確保したうえで、余剰分を投資するのがおすすめです。
退職金の支給時期に関するよくある質問

退職金の支給時期に関するよくある質問として、以下の点を解説します。
- 退職金の支給が遅延する理由は?
- 退職金の増額交渉は可能?
退職金の支給が遅延する理由は?
退職金の支給が遅延する主な理由は、以下のとおりです。
- 企業の資金繰りが悪化している
- 退職金の計算に時間がかかっている
- 書類の手続きに遅延が生じている
- 大量退職が発生している
- 企業と退職者の間で金額の交渉が続いている
- 意図的に支払いを遅らせている
- 退職金制度に変更が生じた
- 企業の合併や買収が生じた
- 経営陣が交代した
- 法的問題や訴訟に直面している
長年勤務した従業員の場合、複雑な計算が必要になり、時間を要する場合があります。人事部門の業務が混み合っていると、退職金の支給手続きが遅れる場合もあります。退職金の支給が遅れている場合は、まず担当者に理由を確認しましょう。状況によっては、労働基準監督署への相談も検討してください。
退職金の増額交渉は可能?
退職金の増額交渉は可能ですが、実現は難しい場合があります。交渉のポイントとして、以下が挙げられます。
- 自分の実績や貢献を具体的な数字や事実で示す
- 退職の意思を伝える前に交渉を行う
- 会社の財務状況や退職金規定を事前に確認しておく
- 感情的にならずに礼儀正しく交渉する
- 有給消化など他の形での補償を提案する
- 交渉結果は必ず書面で残す
事前の準備と適切なアプローチが交渉成功のカギです。上手くいかない場合は、労働組合や専門家に相談するのも一案です。
まとめ

退職金は、一般的企業では退職後1〜3か月以内に支払われます。企業の方針や就業規則、退職理由などによって、支給時期や支給額が変わる場合もあります。退職金の受取方法によって、税金の扱いも変わるため注意しましょう。
退職金がもらえない場合は、会社の担当者へ確認したり、労働基準監督署に相談したりすることが有効です。受け取った退職金は、定期預金や投資信託などで運用できます。リスク許容度を検討し、生活資金や緊急時の資金も確保しておくことが大切です。
支給が遅延した場合や増額交渉について知っておくと、予想外のケースにも対応できます。記事を参考に退職金に関する知識を身に付け、賢く将来の資金計画を立てましょう。
» 退職代行とは?仕組みとメリット・デメリット、利用の流れ








