就職したばかりの20代前半でも、将来の経済的不安を感じることがあります。経済的不安は多くの人にとって深刻な問題です。この記事では、退職金の種類や相場、計算方法、税金、受け取り方を詳しく解説します。記事を読めば、将来の退職金を把握し、賢い資産管理やキャリアプランに役立てられます。
退職金は勤続年数や企業規模、業種によって大きく異なる制度です。退職金を予測して適切な対策を立てれば、経済的不安を軽減できます。
※退職金制度を採用していない企業もあります。その時はご自身で老後の資金を準備しておく必要があります。
退職金の種類

退職金制度には、以下の種類があります。
- 退職一時金制度
- 企業年金制度
- 退職金共済
退職一時金制度
退職一時金制度は、退職時に一括で支給され、勤続年数が長いほど増える仕組みです。企業ごとに規則が定められ、中小企業での導入が多い傾向にあります。会社都合の退職では税制優遇が受けられ、支給額が増えるケースが一般的です。
役職が上がるほど金額も増えますが、経営状況によっては支給が難しくなる場合もあります。近年は、毎月積み立てる年金型の制度へ移行する企業も増えています。長く働く人の意欲を高める一方で、若いうちに転職を考える人には魅力を感じにくい制度です。
令和5年現在、退職一時金・年金制度を採用していない会社が24.8%あります(厚生労働省資料より)。1990年代後半のバブル崩壊時期以降に設立された会社は退職金制度の採用率が低いです。あなたが従事している会社の入社時に説明が無かった場合、念のために確認した方が良いです。
企業年金制度

企業年金制度は、従業員の老後を支える仕組みです。確定給付企業年金(DB)と確定拠出年金(DC)の2種類があります。DBは将来の年金額が決まっており、企業が運用リスクを負うために安心感がありますが、負担が大きく導入が減少しています。DCは従業員が運用商品を選び、結果に応じて年金額が変動する制度です。
企業負担が少なく導入が増えていますが、投資知識が求められます。キャッシュバランスプランは、給付額の一部を確定し、残りを運用結果で調整する仕組みです。企業年金制度を選ぶ際は、将来設計を考え、自分に合った制度の選択が重要です。
運用リスクや年金額の変動を理解し、会社の財政状況も確認して、安定した給付が期待できるか見極めましょう。複雑な制度ですが、将来に備え理解を深めることが大切です。
退職金共済
退職金共済は、中小企業の従業員向けの外部積立型退職金制度で、国や都道府県が運営する公的な仕組みです。退職時に確実に支給され、事業主が掛け金を全額負担します。掛け金は全額損金算入でき、税制優遇の対象となります。金額は月額5,000~30,000円の範囲で選択可能です。退職理由に関係なく支給される点も特徴です。
退職金共済には、以下の4種類の制度があります。
- 中小企業退職金共済(中退共)
- 特定業種退職金共済(特退共)
- 林業退職金共済(林退共)
- 清酒製造業退職金共済(清退共)
転職時には、新しい会社への制度の引き継ぎが可能で、長期的な資産形成に役立ちます。解約返戻金や住宅融資などの付帯サービスがあり、福利厚生の充実に貢献する制度です。
退職金の相場

退職金の相場について、以下の項目に分けて説明します。
- 大企業の相場
- 中小企業の相場
- 業種別の相場
- 勤続年数別の相場
大企業の相場
大企業の退職金相場は一般的に高水準で、平均約2,300万円です。対象は従業員1,000人以上の企業で、役職や勤続年数が増えるほど金額も上がります。部長クラスや30年以上勤務すると、3,000万円を超える場合があります。
業種によっても差があり、金融・保険業は最も高く平均3,000万円以上、製造業や情報通信業は2,500万円前後です。近年は終身雇用の崩壊や成果主義の影響で、同じ勤続年数でも個人差が大きくなっています。男女間で20~30%の差があり、男性の方が高い傾向があります。
中小企業の相場

中小企業の退職金相場は、大企業に比べて低めです。従業員数や業種によって差があり、以下の傾向が見られます。
- 従業員数30人未満:約240万円
- 従業員数30~99人:約340万円
- 従業員数100~299人:約430万円
大企業の退職金の半分~3分の2程度の水準です。勤続20年で300万円前後が一般的ですが、業種や職種によって差があります。製造業や金融業は高めで、サービス業や小売業は低めの傾向です。中小企業の退職金は経営状況や業績に左右されやすく、制度自体がない企業も増えています。
企業規模や業種、経営状況によって異なるため、自社の制度を確認したうえでの将来的な資金計画が大切です。
業種別の相場
退職金の相場は業種によって大きく異なります。業種別の平均退職金相場を以下の表にまとめました。
| 業種 | 平均退職金(万円) |
| 金融・保険業界と公務員 | 700 |
| エネルギー・電力業界 | 600 |
| IT・通信業界 | 500 |
| 製造業 | 450 |
| 建設業と不動産業 | 400 |
| 小売・卸売業と運輸・物流業 | 350 |
| サービス業 | 300 |
| 医療・福祉業 | 250 |
| 教育・学習支援業 | 200 |
退職金は、企業規模や役職、勤続年数によって異なります。近年は退職金制度を廃止・縮小する企業も増えています。業界平均だけでなく、自社の制度の確認が重要です。
勤続年数別の相場
勤続年数が長くなるほど退職金の額も増える傾向があります。一般的な相場は、以下のとおりです。
- 3年未満:1〜2か月分
- 5年:2〜3か月分
- 10年:4〜6か月分
- 15年:8〜12か月分
- 20年:12〜18か月分
- 25年:18〜24か月分
- 30年:24〜36か月分
- 35年以上:36か月分以上
実際の金額は企業によって異なります。同じ勤続年数でも企業規模や業種によって差があり、大企業の方が中小企業より高い傾向です。企業選びの際には、退職金制度も確認しましょう。
退職金の計算方法

退職金の計算方法を以下の種類別にまとめました。
- 基本給連動型の計算方法
- ポイント制の計算方法
- 定額制の計算方法
基本給連動型の計算方法
基本給連動型の退職金は、最終月の基本給を基準に算出され、多くの企業で採用されています。計算式は、最終月の基本給 × 支給倍率 × 勤続年数です。支給倍率は企業ごとに異なり、一般的に0.5~2.0の範囲で設定されます。勤続年数が長いほど倍率が上がる傾向です。
役職や職能資格、会社の業績、退職理由によって変動する場合もあります。勤続年数や役職が反映されやすい一方、最終月の基本給が低いと退職金も少なくなるため、注意が必要です。
ポイント制の計算方法

ポイント制の退職金は、勤続年数や職位に応じてポイントを付与し、退職時の累計ポイントに単価を掛けて算出します。従業員の貢献度を公平に評価しやすい仕組みです。毎年の勤続年数や職位に応じてポイントが付与され、年齢や役職によって加算率が変動します。
業績評価に応じたボーナスポイントや、資格取得・特別貢献による追加ポイントもあります。ただし、退職理由によってはポイントが減算されるケースがあり、慎重な判断が必要です。ポイントに有効期限を設ける企業もあるため、長期的な計画が求められます。
従業員の努力や成果が反映されやすく、モチベーション向上にもつながります。
定額制の計算方法
定額制の退職金は、勤続年数や役職に関係なく一定額を支給する方式です。会社があらかじめ設定した金額を支払うため、計算が単純でわかりやすく、退職金額を予測しやすい点が特徴です。10年以上勤務で100万円、20年以上勤務で200万円など、勤続年数ごとに固定額が決められています。
中小企業や新興企業で採用されるケースが多く、会社の財務状況に左右されにくい点もメリットです。従業員にとっては退職金の見通しが立てやすく、会社側にとっても管理や計算が容易なため、運用しやすい制度です。ただし、長期勤続者には不利になる可能性があります。
退職金にかかる税金

退職金に関連する税金のポイントを以下に紹介します。
- 退職所得控除の仕組み
- 退職金の手取り額の計算方法
- 一括受取と年金形式受取の税金比較
退職所得控除の仕組み
退職所得控除は、退職金にかかる税負担を軽減する仕組みです。勤続年数に応じて控除額が増え、長く働くほど税制上のメリットがあります。控除額の計算方法は、勤続20年以下の場合は1年につき40万円、20年超は800万円+1年につき70万円です。最低控除額は80万円で、勤続年数が短くても適用されます。
障害者として退職する場合は、控除額が100万円上乗せされます。複数の会社からの退職金は合算して計算し、前年以前に受け取った分も通算可能です。退職所得控除額は退職金から差し引かれ、残額に課税されます。退職所得控除により、退職者の税負担が抑えられます。
退職金の手取り額の計算方法

退職金の手取り額を正確に計算するには、いくつかの手順が必要です。計算手順は、以下のとおりです。
- 退職所得控除額を求める
- 退職所得金額を算出する
- 所得税を計算する
- 復興特別所得税を求める
- 住民税を算出する
税金を差し引けば、手取り額がわかります。控除額は年齢や勤続年数、退職理由によって異なり、受取方法によっても税額が変わります。社会保険料の控除も考慮し、正確な手取り額を確認しましょう。
一括受取と年金形式受取の税金比較
一括受取と年金形式受取では、税金の計算方法が異なります。一括受取は退職所得控除後の金額に2分の1課税が適用され、年金形式受取は毎年の受取額に雑所得として課税されます。一括受取のメリットは、大きな金額をまとめて運用できる点です。ただし、多額の税金が発生する可能性があります。
年金形式受取は安定した収入を得られ、税負担を分散できる点がメリットです。長期的には税負担が軽減される場合もあります。高額な退職金は年金形式の方が税制上有利で、低額なら退職所得控除の範囲内で一括受取が有利になります。
受取方法を選ぶ際は、生活設計や収入見込み、投資・運用の知識、健康状態などを考慮しましょう。税制改正の可能性もあるため、最新情報の確認が重要です。
退職金が支払われるタイミングと手続き

退職金が支払われるタイミングと手続きについて、以下の項目ごとに解説します。
- 退職金が支払われるタイミング
- 退職金を受け取るための手続き
退職金が支払われるタイミング
退職金は通常、退職日から1か月以内に支払われますが、会社によって異なります。定年退職は退職日当日に支給されるケースが一般的です。2〜3か月後に支給されるケースもあり、年金形式で分割する企業もあります。支払い時期は退職金規定に明記されていますが、資金繰りの影響で遅れる場合もあり、6か月以内が一般的です。
自己都合か会社都合かで時期が異なり、経営状況によって分割払いになる可能性もあります。退職金の支払いタイミングは会社ごとに異なるため、事前に確認してください。不明点があれば、人事部門に相談しましょう。
退職金を受け取るための手続き
退職金を受け取るには、いくつかの手続きが必要です。退職届を提出し、正式に退職の意思を伝えた後、以下の手順を進めると、退職金をスムーズに受け取れます。
- 支給額を確認する
- 必要書類を準備する
- 受取方法を選択する
- 振込先の銀行口座を指定する
- 請求書を提出する
手続きには退職証明書や源泉徴収票などの必要書類の準備が必要です。受取方法は一括か分割かを選び、請求書を提出したら、支払日を確認しましょう。退職後に住所変更があれば、連絡先を更新してください。退職金を受け取ったら、金額を確認して税金処理をしましょう。
退職金が相場よりも少ない場合の対策

退職金が相場より少ない場合、将来の生活に備えて、以下の対策を検討しましょう。
- iDeCoを活用する
- NISAを活用する
- 個人年金保険を検討する
iDeCoを活用する
iDeCoは、個人型確定拠出年金の略称で、将来の退職金を補完する手段です。制度を活用すると、税制優遇を受けながら長期的な資産形成が可能になります。iDeCoの主なメリットは、以下のとおりです。
- 毎月の掛け金を積み立てられる
- 掛け金を所得控除の対象にできる
- 運用益を非課税にできる
- 受け取り時に退職所得控除や公的年金など控除を適用できる
60歳まで引き出せないため、計画的に老後資金を準備できます。若いうちから老後資金を確実に準備するために役立ちます。運用商品を自由に選べるため、自分の投資スタイルに合わせた資産運用が可能です。企業型確定拠出年金との併用には制限があり、年間拠出限度額は職業によって異なります。
NISAを活用する

NISAは、退職金の運用に活用できる非課税投資制度です。年間120万円まで非課税で投資でき、資産形成に役立ちます。NISAにはつみたてNISAと一般NISAの2種類があります。つみたてNISAは20年間非課税で長期投資向け、一般NISAは5年間非課税で幅広い金融商品に投資可能です。
NISAを活用すると、株式投資信託や上場株式への投資を通じて資産形成を目指せます。複利効果を活かせるため、長期的な資産増加も期待できます。少額から始められるため、投資初心者にもおすすめです。ただし、リスクを抑えるためには、複数商品への分散投資が重要です。
NISAを利用するには、金融機関や証券会社で口座を開設する必要があります。退職金の運用手段として、NISAは有効な選択肢の一つです。
個人年金保険を検討する
個人年金保険は、老後資金を補う手段として有効です。将来の生活設計に合わせて柔軟に設計できるため、早めの準備が推奨されます。積立型と一時払い型があり、積立型は毎月積み立てる方式、一時払い型は一括で支払う方式です。経済状況やライフプランに応じて適した方法を選びましょう。
個人年金保険には、税制優遇措置が適用される場合があり、節税効果が期待できます。受取方法は一時金または年金形式から選択可能で、運用リスクは保険会社が負います。支払い期間や受取開始年齢を選べるため、ライフプランに合わせた設計が可能です。
ただし、解約返戻金が低くなる場合があり、インフレリスクも考慮する必要があります。他の金融商品と比較しながら、自分に合った選択をしましょう。
まとめ
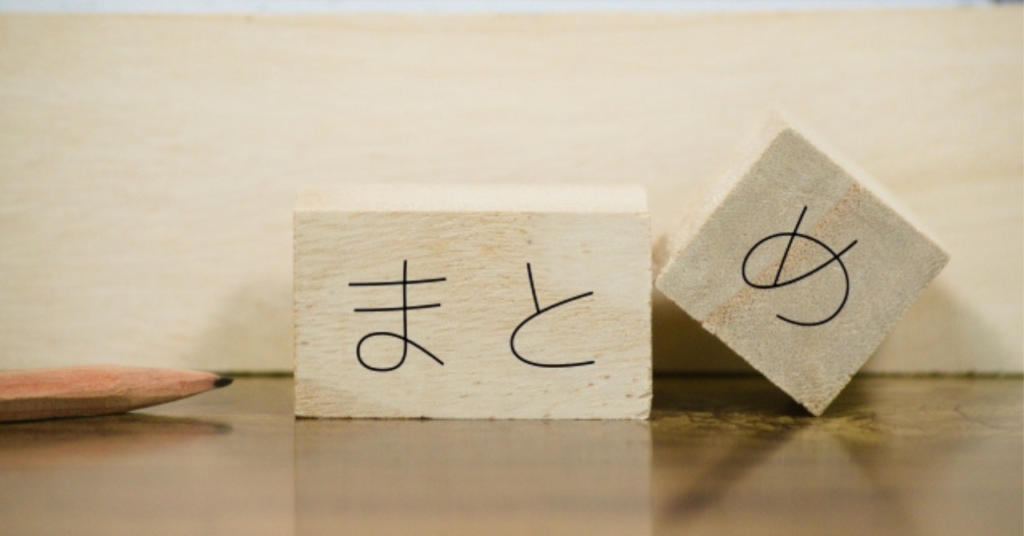
退職金制度は、主に一時金制度や企業年金制度、退職金共済の3種類に分けられます。支給額は企業規模や業種、勤続年数によって異なるため、退職金規定の確認が重要です。計算方法には、基本給連動型やポイント制、定額制などさまざまな種類があります。
税制面では、退職所得控除が適用される制度ですが、受取方法によって税額が変わる仕組みです。退職金は通常、退職後数か月以内に支払われますが、受け取るには手続きが必要です。退職金が少ない場合は、iDeCoやNISA、個人年金保険で補う方法もあります。退職金制度を理解し、将来に備えた準備を進めましょう。








